|
|
|
科学哲学ニューズレター |
![]()
No. 29, October 4, 1999
| Book Review by Soshichi Uchii | Japanese Translation of Martin Harwit, An Exhibit Denied--Lobbying the History of Enola Gay, Misuzu shobo, 1997 | |
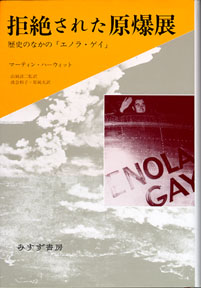 |
 |
|
Editor: Soshichi Uchii
書評
マーティン・ハーウィット『拒絶された原爆展──歴史の中の「エノラ・ゲイ」』、山岡清二監訳、度会和子・原純夫訳、みすず書房、1997年。
広島への原爆投下に使われたB29爆撃機、エノラ・ゲイを中心にすえたスミソニアン航空宇宙博物館の原爆展が、退役軍人や空軍協会をはじめとする各方面からの袋だたきにあって中止に追い込まれ、企画責任者だった館長のハーウィットが辞任した事件(1995年)はまだ記憶に新しい。本書は、その一方の当事者ハーウィット自身の手になるドキュメンタリーである。書評で取り上げるには少し古い翻訳書であるが、わたしが現在行なっている講義「科学者と社会」のテーマと関連が深いので、そのさわりを紹介しておこう。なお、この本と関連が深いのは、今年の6月に刊行された「日本原爆論大系』(坂本義和・庄野直美監修、日本図書センター、1999)であり、とくに第7巻『歴史認識としての原爆』(岩垂・中島1999)第4章「スミソニアン原爆展問題」である。
まず、原爆投下に関する日米の認識と価値判断の大きな違いを、ハーウィットの本に収録されている資料によって確認しておこう。
エノラ・ゲイは戦争を「一夜にして」終わらせたという事実の象徴であり、日本の各都市への焼夷弾爆撃で戦争を終わらせることができるであろうというルメイの主張を骨抜きにした航空機である・・・。実際、焼夷弾爆撃で戦争を終わらせることもできたでしょう。ただし終戦がいつになるかはだれにも分からず、その間にも日本侵攻計画は進行していました。 原爆を使うというトルーマン大統領の勇気ある決断により、その論争から「いつ」という言葉が取り除かれ、代わりに「いま」という言葉の使用が始まったのです。戦争が即時終結したおかげで、日本侵攻を行なった場合失われたはずの連合軍と日本側双方の人命数百万が救われたわけですが、おそらくそれと同様に重要だったのは、対日和平交渉に加わりたがったロシア人の企みが阻止され、日本には「ベルリンの壁」ができなかったという事実です。(ex-captain of B29, Donald C. Rehl, letter to Harwit, December 2, 1992)
広島と長崎への原爆投下はいまなお日本人の意識に深く刻み込まれておりまして、ユダヤの人々にとってのホロコーストと同じなのです。(日本テレビ社長、高木盛久、ハーウィット宛書簡、1988年11月28日)
この二つの引用は、それぞれの国で支配的な見解の一例にすぎない。爆撃機の元機長レールは原爆投下はよかったと賞賛するのに対し、日本人の一般的な態度を代弁する高木は原爆投下は戦争犯罪に匹敵する悪だと見なしている。しかし、二つの引用に示されている二つの対立する評価(価値判断)は、それぞれが前提している事実認識を改善することで、ある程度歩み寄れるはずである。「事実認識」とは、多くの論者が危惧するような、五十年前の出来事を現代の知識と観点から判断するという意味での認識ではない。五十年前に、あの重要な決定をする立場にいた人々に利用できたはずの「事実認識」を再現しようという努力を指す。ハーウィットをはじめとするスミソニアンのスタッフは、解禁された文書など種々の史料を示すことでこの努力を行なったことがよくわかる。
レールの見解に示された「事実認識」は、少なくとも「救われた人命」の見積もりについては、単なる神話を引くだけでなく、さらに大きな誇張まで加えている。スミソニアンが最初の展示台本で採用していた数字は、「日本の南の島である九州への侵攻作戦が行なわれた場合の推定死傷者数として・・・1945年6月18日の会議でマーシャル陸軍元帥、キング海軍元帥、大統領付き幕僚長を務めるレーヒ提督がトルーマン大統領に提示した数字」(ハーウィット1997、270)であり、マーシャルとキングの推定は「作戦開始後の最初の30日で三万人から五万人」である。これは、「死者」の数ではなく「死傷者」の数であることに注意されたい。また、レーヒが示した数字は沖縄戦から推定されており、「九州の作戦全体で最高二十六万八千人の死傷者、そのうち五万人が戦死」と解釈される(後の歴史家の分析によれば下方修正され、死傷者六万三千人となるはず。ハーウィット1997、432)ものであった。日本側の死者の数を入れても、レールの数値とは二桁も異なる。
これに対し、広島と長崎では、1945年末までの死者はあわせて二十一万人で、被爆者の総数はそれの約二倍になるはずである。しかも、大半は非戦闘員であることを忘れてはならない。岩垂・中島(1999)に収録されている斉藤道雄氏によれば、百万人神話の出所は元陸軍長官スティムソンの1947年の論文だという。トルーマンが自分の決定の正当化に都合のよいこの数値を演説などで使ったため、いまだにこの神話がまかり通っているのである。スティムソンは、後の資料でもみるように、優れた見識の持ち主であったらしい(それゆえオッペンハイマーなども感銘を受けた)が、老練な政治家でもあったことは疑いがない。
他方、日本側の見解にも批判と分析が必要である。これもすでに多くの人が指摘してきた、いわば「常識」レベルの話になるが、被爆だけをとりだして「戦争犯罪に匹敵する悪」と即断することは明らかに不当である。今次の戦争は、日本が中国大陸や東南アジアで始めた侵略に少なくとも一つの重要な起源をもつ。したがって、それこそ何の罪もない多数のユダヤ人たちのホロコーストと同列に置くわけにはいくまい。これは、(原爆開発をルーズヴェルトに進言したことを後悔したとされる)アインシュタインや武谷三男らによってつとに指摘されてきたことである。そして、同じようなことをもっと具体的な体験を通じて感じさせてくれるのは、これも岩垂・中島(1999)に収録されている直野章子の体験談である(同、510、529-532。彼女は、スミソニアン騒動の後、アメリカン大学で原爆の被爆資料展開催に尽力した)。中国人あるいは東南アジアの人々の目には、原爆投下は「解放」と映ったのである。原爆をめぐる認識と評価の溝は、日米間だけに注目していては埋められないであろう。
しかし、スミソニアンの展示台本を見ると、このあたりの事情や歴史的経緯についてもバランスのとれたプランであったことは疑いがない。ハーウィットの本では、もともと物理学者であった著者の綿密な気配りと学究肌ぶりが伝わってくる。「岐路──第二次世界大戦の終結、原子爆弾、そして冷戦の起源」というタイトルをつけられた展示は五部構成となっていた。第一部「終結へ向けての戦い」では、太平洋戦争に先立つ出来事から戦争末期にかけての事情が説明される。原爆投下を位置づける一つの脈絡として、「戦略爆撃」に注目するのは重要なポイントである(これはリチャード・ローズの名著『原子爆弾の誕生』でも指摘されている)。
戦略爆撃とは、敵の軍需生産能力を破壊するための敵本土への空爆である。他方、戦術爆撃とは、陸戦あるいは海戦に投入された戦力の直接的支援を行なう。大規模な戦略爆撃が初めて出現したのは第二次世界大戦時であり、それには二つの形態があった。軍需生産拠点としての重要度に応じて選ばれた特定の目標に対する昼間爆撃・・・と、労働者の住宅(と生命)を破壊し、それによって敵の志気を低下させることを目的として通常夜間に行なわれる、都市全域へのいわゆる「地域爆撃」である。・・・地域爆撃(「都市破壊」)については、その道義性と、それがもつとされる軍事的効果とをめぐっていまなお激しい議論がある。・・・三十年戦争の終結から第二次世界大戦の地域爆撃作戦まで、計画的に都市住民を標的とすることは、軍事行動における原則というより例外であった。(ハーウィット1997、73-4、ソーターのドラフトよりの引用)
第二部の「原爆投下の決定」ではマンハッタン計画とトルーマン大統領の原爆投下決定に至る過程が、解禁された文書とともに示される。展示の目玉はプルトニウム爆弾の巨大な爆弾殻である。第三部「原爆投下」では、エノラ・ゲイの胴体前部とウラニウム爆弾の爆弾殻が展示される。B29の製造経緯と投下作戦を実行した第509混成群団にも触れられる。
反対派が削除を要求した第四部「グラウンド・ゼロ」では、広島と長崎の地上の光景が両市からの被爆資料やビデオとともに示される。これは、空軍協会『エア・フォース』誌の編集長コレルが、被爆写真はあまりに生々しく被害者への感情移入を誘う(斉藤道雄による記述、岩垂・永中島1999、442)ので「感情センター」だと見なし、エノラ・ゲイと一緒に展示するのはまずい(つまり、自分たちがあらかじめもっている価値判断を揺るがせるような効果をもたらすのでまずい)と反対した部分である。そして、最後の第五部「広島と長崎の遺産」では戦後の核軍備競争と核拡散に触れる。
さて、ハーウィットのこの本で参考になるのは、展示のために集めた資料がふんだんに示されていることである。とくにわたしの注意を引いたのは、陸軍長官スティムソンが新大統領トルーマンに原爆のことを説明する際に使った覚え書きである。ハーウィットもこれを重視しているので、長くなるが、ほとんど全文を引用したい。
スティムソンのトルーマン宛の覚え書き(1945年4月25日、同書253-256)
1 四ヶ月以内にわれわれが人類史上もっとも恐ろしい兵器を完成することはほぼ確実である。すなわち、一発で一つの都市全体を壊滅させる爆弾である。
2 その開発には英国と共同で当たったが、物理的には現在、合衆国が、これを製造し使用するのに要する資源、手段を握っており、他のいかなる国も、ここ数年間はこの地位に到達することはできないであろう。
3 しかし、われわれが無期限にこの地位にとどまりえないことは事実上確かである。
a その発見と製造に関するさまざまな断片的知識は、すでに多くの国の多数の科学者たちの間で広く知られている。ただし、われわれが開発した行程のすべてを知る科学者はごく少数に限られる。
b 現在の方法によって製造するには、科学的にも工業的にも多大の努力と資源とを必要とし、目下のところ、そのいずれをも所有し知っているのは、主として合衆国と英国である。しかし将来、はるかに容易で安価な製造法が科学者によって発見され、あわせてもっと広く流通している原料が使用されるようになる可能性はきわめて高い。その結果、将来は、小国または小グループでさえ製造しうるようになる可能性、あるいは少なくとも大国がはるかに短期間に製造できるようになる可能性はきわめて高くなるであろう。
4 この結果、将来には、野心をもつ国またはグループがこのような兵器を秘密裡に製造し、突如としてそれを、はるかに大きな規模と物質力をもちながらも警戒を欠いた国またはグループに対して使用し、壊滅的な打撃をもたらすこともありえよう。この兵器の威力をもってすれば、きわめて強大な国といえども警戒心を欠く場合には、わずか数日にして、はるかに小さな国に征服されてしまうであろう。ただし、今後数カ年内に生産を開始するようになる国は、おそらくロシアだけであろう。
5 技術の進歩に対する道徳的進歩の現状からすると、世界は究極的にこのような兵器によって意のままにされることになるであろう。つまり、近代文明は完全に破壊されてしまいかねないのである。
6 これから検討されることになる世界平和機構がどのような形態のものになるにせよ、わが国の指導者たちが、この新しい兵器の威力を認識することなしに、その問題に取り組むことは、およそ非現実的なことになるであろう。これまで考えられてきたいかなる管理体制も、この脅威を制御するには十分ではない。この兵器の管理が一国内においても国家間においても、もっとも困難な問題となることは疑いないところであり、従来まったく考えられなかったような徹底的な査察権と国内管理とが必要となるであろう。
7 さらに、この兵器に関するわれわれの立場からして、他国にもこの兵器に関与させるか、もし関与させるとすればいかなる条件の下でかという問題が、わが国の大きな外交課題となるであろう。また、今次戦争およびこの兵器開発における指導的立場に伴い、われわれには一定の道義的責任が課されているのであって、この責任を回避することは、文明の破壊をもたらす重大な責任を免れないであろう。
8 他方、この兵器の適正な使用に関する問題が解決されるならば、世界の平和とわれわれの文明を救う方向へと世界を導く機会を得ることができよう。
9 グローヴズ将軍の報告書で指摘されているように、機密保持がもはや効力を失った際に、わが行政府および立法府がとるべき措置について勧告する特別権限をもつ委員会を設立するための準備が進められている。この委員会はまた、戦後問題を予想し、あらかじめ陸軍省がとるべき手段についても勧告することになるであろう。もちろん、同委員会の勧告はすべて、まず大統領に提出されることになるであろう。
ハーウィットも注目するように、4以後の項目はスティムソンの慧眼を示唆するに十分である。ボーアに強く影響され、核の国際管理の問題に腐心したのはオッペンハイマーであるが、この時期スティムソンはまだオッペンハイマーに会っていない。しかし、この老政治家は、米ソの軍拡競争を見越している(項目4)し、核の問題が国際政治の中心課題になることも認識している(項目5、6、8)。さらに、後のフランク・リポート(45年6月11日)やシラードの請願書(45年7月17日)に先立って、政治家の立場から合衆国の核に対する道義的責任について言及している(項目7)。 道義的責任といえば、トルーマンの日記からの抜粋も資料として興味深い。投下決定の前後に、人間としての合衆国大統領が何を考えたかを窺い知る一助となるからである。
トルーマンの日記(1945年7月25日)
この兵器はいまから八月十日までの間に日本に対して用いられる予定だ。私は陸軍長官スティムソン氏に対し、目標は兵士と水兵にすべきであり、女や子供に用いてははならないと言っておいた。たとえ日本人が野蛮で、残忍かつ冷酷、しかも狂信的であっても、共通の福祉を世界にもたらす指導者たるわれわれとしては、この恐るべき爆弾を新旧いずれの首都にも投下することはできない。彼と私は同じ意見だ。目標は純粋に軍事的なものとなろう。そしてわれわれは、ジャップに対し、降伏して人命を救うよう要求する警告の声明を発するつもりだ。連中がそんなことをするとはとうてい思えないが、連中に機会を与えてやろう。ヒトラーやスターリンの一味がこの原子爆弾を発明しなかったのは、世界のためにまことに結構なことだった。およそこれまでになされた発見の中でもっとも恐るべきものと思われるが、最も有効に用いることもできるのだ。
しかし、「目標は兵士と水兵にすべき」だという注意は、大統領にしては原爆をあまりに知らなさすぎる。また、次の手紙は長崎に原爆が投下された直後に書かれたものだが、彼の人間的懸念を示す(ハーウィット)というよりは、われわれには、まったく不必要な二発目を落としたことへの、まずい言い訳のように聞こえる。
トルーマンのリチャード・ラッセル宛の手紙(1945年8月9日)
私自身としては、一国の指導者たちが「頑迷」であるがために、その国民すべてを抹殺する必要があるというのは、たしかに遺憾なことと考えます。特に申し上げておきますが、絶対に必要でないかぎり、私としてはそうするつもりはありません。ロシア人が参戦すれば、日本人はすぐにも降伏するだろうというのが私の考えです。私のめざすところは、できるだけ多くのアメリカ人の命を救うことですが、日本の女性や子どもに対しても人間としての感情を抱いております。
いずれにせよ、こういった資料をたくさんそろえ、多角的に配慮し、粘り強く圧力団体と交渉を続けたハーウィット館長がついに展示をあきらめ職を辞した無念さはよくわかる。しかし、全体の叙述は個人的感情をできるだけ押さえた冷静なものになっていて読者の共感を呼ぶ。ただ、彼が時折もらす「創立者スミッソンだったならわたしの展示を支持してくれただろうに」という感想は、スミッソンではなく、スミソニアンの初代長官ジョゼフ・ヘンリーに言及した方がよかったかもしれない。ヘンリーは、基礎研究の重要性を一貫して主張し、議員と渡り合うことも辞さなかったのである。
文献
ハーウィット(1997)『拒絶された原爆展』みすず書房、1997。
岩垂弘・中島竜美編(1999)日本原爆論大系『歴史認識としての原爆』、日本図書センター、1999。
ローズ(1995)『原子爆弾の誕生』上下、紀伊国屋書店、1995。
October 4; last modified, October 12, 1999. (c) Soshichi Uchii
