|
|
|
科学哲学ニューズレター |
![]() No.7, January 1995
No.7, January 1995
Associate Professor Nominated
Book Review: Y.Murakami's What is the Scientist? (S.Uchii)
Our Courses for the Coming Year
A Happy New Year! 1995
●☆●☆●☆●☆●
当講座の助教授決定!
さる1月12日(木)の教授会で、かねてより選考中であった科学哲学科学史講座の助教授として、伊藤和行氏の任用が決まった(4月1日着任予定)。以下に略歴と業績とを紹介しておく。
伊藤和行(1957-)北海道大学理学部物理学科卒業('79)、東京大学大学院理学系研究科(科学史・科学基礎論)博士課程修了('85)。1984年から1987年までイタリアのフィレンツェ大学およびフィレンツェ科学史博物館に留学。その後、学術振興会特別研究員、東京圏の多くの大学で非常勤講師。主な研究領域は、ガリレオを中心とした近代物理学形成史とルネサンスの自然哲学。近代科学の本流だけでなく、ヘルメス主義の伝統に属する占星術、錬金術、魔術関係の文献も丹念にこなし、芸術と人文主義の流れにも目配りの利いた幅広い研究が特色。
論文----「ジョルダーノ・ブルーノの地動説」『科学史研究』142、'82。「ガリレオの運動論とその背景」『科学史』(佐々木力編)弘文堂、'87。「ガリレオの斜面運動の原理」『イタリアーナ』16、'87。「ガリレオとピサの斜塔」『イタリア図書』2、'88。「ルネサンスの技術家」『講座科学史1
西欧科学史の位相』(伊東・村上編)培風館、'89。「人文主義・芸術・科学---イタリア・ルネサンス科学新考」『思想』785、'89。「トリチェッリの実験と真空の存在」『自立する科学史学』北樹出版、'90。「混沌たる自然---ルネサンスの魔術的自然観」『理想』649、'92。「太陽崇拝思想と太陽中心説」『ルネサンスの知の饗宴』(佐藤三夫編)東信堂、'94。その他、ガリレオの原典翻訳を含め翻訳多数。
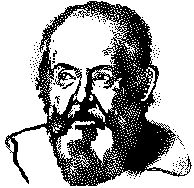
"Eppur si muove."
ガリレオ・ガリレイ(1564-1642)
書評 (岩波『科学』65 [1995-2] に掲載)
村上陽一郎『科学者とは何か』新潮選書、1994年10月刊。
著者の村上陽一郎についてはいまさら紹介の必要もないであろう。彼は、東大先端科学技術研究センターで「科学技術倫理」という研究分野を担当し、同センターの所長も務めている。本書のタイトルにもなっている「科学者とは何か」という問いの背後にある本当の問いは、「科学者とはどうあるべきか」という、彼の現在の研究分野の根幹に関わる問いなのである。
冒頭の第1章では、文学者唐木順三が遺作で取り上げた「科学者の社会的責任」の問題が手短に素描される。この問題が取り上げられるとき必ず言及されるのは、核兵器開発の「マンハッタン計画」である。この計画に直接参加した科学者、参加しなかった科学者も含めて、科学者の反応は二つに大別される。第一は、核兵器の開発に物理学が手を貸したことを「罪」ととらえ、科学者としてそのような「罪」を犯す危険性があることを認めてある種の「共犯意識」を持つグループである。第二は、このような開発やそれにつながる研究を科学のその時々の課題を解決するという観点からのみ眺め、核兵器やその使用に関する倫理的判断は科学研究とは無関係だと見なすグループである。リチャード・ファインマン(核開発に参加した)や湯川秀樹を含め、大多数の科学者は第二のグループに入る。
著者の企ては、この第二のグループが科学者の典型だと見なし、そのような意識を共有する一種の職能集団としての科学者について、まず「行動規範」、「科学者の共同体の形成」、「行動様式」、および「倫理問題」を明らかにすることである(第2〜5章)。このように、「現にある」科学者像を提示した後、著者は「これからあるべき」科学者像を模索する作業に入る(第6章)。著者がそのための足がかりとするのは、三つの事例である。(1)核開発の可能性と危険性とをいち早く察知し防ごうとして他の物理学者たちに働きかけた一方、原爆の完成後は対日戦での使用を止めようとする良心的行動を取ったハンガリー出身の物理学者レオ・シラード。(2)組み替えDNAの技術およびそれを利用した研究の危険性と対策を論じるため、1975年にカリフォルニアで開かれた「アシロマ会議」とその成果。(3)今世紀後半になって深刻になってきた環境問題と、その解決のために求められる科学のありかた。最終第7章では、科学者の「責任のとり方」についていくつかの「好ましい方向」を探る考察が行なわれる。
以下では、いくつかの個別的論点に立ち入ってみよう。まず、十九世紀の西欧社会に出現した職能集団としての科学者の「行動規範」とは何だろうか。一言でいえば「自由競争」でしかなかったと著者は言う。科学者の仕事は研究であり、その研究が自由競争に任されている。「ということは、研究に対する抑制や規制の規範は、科学研究者の共同体の内部機構としては存在していない」(p.14)ことになる。科学者集団は、先輩格である中世以来の職能集団、つまり医師、聖職者、法曹家などと違って「無責任
態勢」をその特徴とする、というのが著者の見方である(科学者の側から、「人文・社会系の研究者はもっと無責任ではないのか」という反応が聞こえてきそうである)。そしてこの見方が本書の基調を決定している。
それでは、そのような「無責任態勢」からの脱却を目指す提案とその根拠はどうなるのだろうか。著者が足がかりとした第一の事例のシラードは、その聡明さと行動力とで読者に感銘を与えるが、「科学者集団」のあるべき姿の基準としては標準が高すぎるという批判が出よう。環境問題にいち早く警鐘を鳴らしたレイチェル・カーソンについてもしかり。この種のヒーローやヒロインを「あるべき科学者像」として賛美しただけでは問題の解決にはなるまい。では、第二の事例「アシロマ会議」についてはどうか。この会議の結論は、実験材料の安全化をはかるため、自発的に「ガイドライン」を作って一部の実験を自粛するという方向を決めたことであった。また、この分野の研究に関して、研究者が所属する機関付属の評価委員会(Institutional
Review Board、略してIRB)が最も積極的に活用されるという制度的副産物ももたらした。この委員会には必ずその分野の専門家以外の委員が含まれなければならず、この委員会の認可がない研究は業績として認められない。著者は、これら二つの成果を産んだこの会議を、科学者共同体の歴史のなかでの画期的な出来事と評価する。すなわち、(1)「自由競争」に制限をかけ、(2)科学的業績の評価において貫かれてきた「同僚評価(ピア・レヴュー)」の原則を破って非専門家にも開かれた研究審査の制度を導入した(しかし、安全性の評価と研究業績自体の評価とは区別すべきではなかろうか?)、という点で「無責任態勢」を改める方向性が打ち出されたと見るのである。これを受けて、「外に向かって」開かれた研究態勢を作り、未来に対しても「責任ある」科学研究を行なうべきだと示唆される。
最後に、評者の感想を一言つけ加えておきたい。「科学者とは何か」という問いも、「科学者の社会的責任」の問いも、もっぱら科学者集団を外から眺めるという社会学的な観点からのみ扱われていることが気になる。科学の内在的な特徴づけを目指す「科学とは何か」という問いかけは行なわれない。しかし、科学者集団の「無責任態勢」を厳しく論難し、「ノーベル賞はいらない」と断じる著者の「科学者評価」あるいは「科学評価」の基準は、後者の問いを避けて本当に明らかにできるのだろうか。唐木順三の問いにかえって言えば、われわれが知りたいのは、単なる「人間の社会的責任」とは区別された、科学と科学者の役割に即した「科学者の社会的責任」なのである。著者の議論では、「科学者としての」行動規範と「人間としての」行動規範との違いがわかりにくくなるという印象を評者は受けた。著者の思い切った判断は傾聴に値するものの、その判断の背後に隠されている基準をもう少しあからさまにする努力があってよかったのではなかろうか。(内井惣七)
来年度の講義予定
○講義※「科学哲学入門」(内井)金4
○講義※「科学史概論」(松尾)月3
○研究「物理学の哲学(空間と時間)」(内井)
金3
○研究「17世紀の西欧科学」(伊藤)水2
○研究 越野(現代史学と共通)
○研究 西村(社会学と共通)
○研究「科学論争と科学論」(横山)集中
○論理学演習(内井)火3
○演習「Boyd, Philosophy of Science」(美濃)木3
○演習 薮木(哲学と共通)
○演習 小林(哲学と共通)
○演習 宗像(哲学と共通)
○演習「T.L.Hankins, Science and the Enlightenment」 (伊藤)前期 水3
○演習「d'Alembert, Discours pr四iminaire de l'Encyclop仕ie」(伊藤)後期 水3
○演習「科学哲学科学史セミナー」(内井・伊藤) 火4 (専攻4回生は必修)
○講読※「ホール『生命と物質−−生理学思想の歴 史』」(伊藤)木2
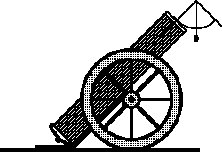
編集後記 来年度からは、科学哲学と科学史の両輪が一応そろって、本格的な教育研究ができることを期待したい。(95.1.13/ 内井惣七/文・カット)
→ Newslet.6
→ Newslet.8
→ Newslet.index
Last modifed March 24, 1999. webmaster
