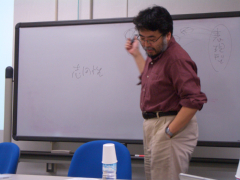|
| PaSTA TOP | 趣旨 | メンバー | 若手育成プロジェクト | Newsletter | COE TOP |

|
PaSTA 及び「哲学系若手研究者育成プロジェクト」研究会の電子メール通知をご希望の方は研究員の佐野までご連絡下さい。
PaSTA の研究会案内の website は、こちらです。
哲学系若手研究者育成プロジェクトは、終了いたしました。 これまでの活動については、 下記の ProjectΦ Newsletter にまとめてあります。 あわせてご覧ください。
ドキュメントのフォーマットはPDFです。閲覧用Acrobat Readerはこちらからダウンロードできます。
Newsletter には、各発表者の詳細な要旨のほかに、発表後に頂いた感想・コメントも掲載しております。 どうぞご覧ください。
日時:3月3日(土)午後2:00-6:00
会場:京都大学文学部東館4階 COE研究室
オーガナイザー: 北島雄一郎 氏(四天王寺国際仏教大学 非常勤講師)
司会:伊藤和行 教授 (京都大学 文学研究科)
講演:
Which can provide a better explanation for the scientific activity, realism or empirical constructivism, an anti-realistic position notably held by Bas Van Fraassen? In this presentation, our attention will be focused on one of the most basic scientific activities; i.e., measurements of the speed of light, and in particular the processes of combinations of divergent measurement results with different apparatus and theoretical backgrounds to obtain its 'standard' value. I would argue that while empirical constructivism cannot make sense this combination process, realism can, and hence the latter rather than the former can provide a better explanation for that.
科学的実在主義とは、我々が直接観測できないものが我々とは独立に存在していて、そのような実在を科学理論を通して認識できると考える立場である。本発表では科学的実在主義が妥当であるという前提のもとで、量子力学が記述する実在とは何かを考察する。量子力学の解釈問題を検討することによって、量子力学が記述する実在の要素には物理的実体と物理的実体間の関係からなる構造が含まれ、物理的実体の性質を実在の要素として考えることはできないと主張したい。
Birkhoff-von Neumann 流のいわゆる量子論理は,量子力学の基礎的問題の 分析のツールとして,或いは非古典論理の一種として,いくつかの興味ある 話題を提供してはいるが,量子系の動的側面を扱えないし,また含意結合子 の非存在などもあり,十分とはいえない.本発表では,伝統的な量子論理に 代わる新しい「量子力学の論理」について,古典論理や直観主義論理など にみられる証明・計算・物理の間の対応関係を足がかりに,その可能性を 検討していきたい.


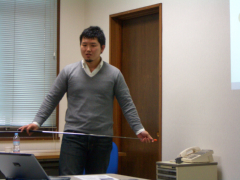
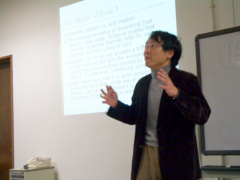




日時:1月13日(土)午後2:00-6:00
会場:京都大学文学部東館4階 COE研究室
オーガナイザー: 大西琢朗 氏(京都大学 博士後期課程 哲学専修)
講演:
ダメットは、「意義」と「意味」の相違や「意義」の必要性、そ して「意義」が単なる記述ではないことなどをいくつかの箇所で論じて いる。その議論は、ダメット自身の言では、フレーゲの議論の解釈であ るとされているにもかかわらず、フレーゲの議論とは大分異なっている ような印象を与える上に、ひどくわかりにくいものとなっている。報告 では、その間の事情を検討し、そこから「意義」についての従来とは異 なる理解の可能性を引き出してみたい。
フレーゲは複合表現の意義(Sinn)に関して、文脈性と合成性という一見相反する ふたつの原理を主張したとされる。これらの原理が互いに整合的であるのかについては、ダメットを始め多くの論者がその理解を試みてきた。本発表では、フレーゲの体系に見いだされる「文法」の特徴を概観することで、この問題について考える手がかりを模索したい。
ガレス・エヴァンズはThe Varieties of Referenceにおいて、単称思想(特定の一 つの個物についての思想)一般の枠組みに関して、フレーゲ-ダメット流の理想的検 証主義の限界を指摘し、そのオルタナティブを提案している。本発表ではエヴァンズ のオルタナティブと理想的検証主義の相違点を明確にした上で、前者の妥当性を検討 する。








日時:12月16日(土) 午後2:00-6:00 (予定)
会場:京都大学文学部東館4階 COE研究室(文学部東館4階北東)地図
オーガナイザー: 出口康夫 氏 (京都大学)・狩野 裕 氏 (大阪大学)
講演予定者と演題:
因果関係を統計的に推定する場合、ある事象eが生じる確率を別の事象cの生起・不生起によって条件づける条件つき確率の比較が、最初の手がかりとなる。けれども、「シンプソンのパラドックス」がつねに生じる可能性によって、そうした条件つき確率の比較は因果推定の手がかりにはならない、という見方が現れざるをえない。もしそうなら、因果関係とはどのように認識されるべきなのか。因果、確率、統計をめぐる基本的謎に少しでも迫りたい。
What is statistics for? What difference has it made to science? In an attempt to answer these questions, I will take a historical approach; that is, to see how scientists tested their hypotheses before and after the introduction of statistics into science. Cases to be examined include Newton's alleged confirmation of his prediction of the ellipticity of Jupiter in the light of Pound's observations in the third edition of his Principia (Book III, prop. 19) and Eddington's alleged confirmation of Einstein's general relativity theory through his eclipse expedition in 1919.
統計学は、科学的な真理・事実を認識するための実践的な技法と言える。論理実証主義認識論に限界が見え、より洗練された認識論が広く受け入れられている。しかしベイズ法は、より古い直観的推論の枠組みで捉えられるので、今日の認識論を支える技法には到底成り得ない。ところが、高次元母数の推測では、幅広く受け入れられている。この著しい乖離の中に科学的な認識論の一つの突破口が見える、と考えている。最近研究しているハイブリッド型ベイズ法を加えて考察した。
推測統計学の基礎を考案したうちの一人として,フィッシャーを挙げることができる.フィッシャーによる統計学の立場は,現在主流的な立場であるネイマン・ピアーソン学派やベイズ統計学派と異なり,検討されることが少ない.本発表では,フィッシャーが考えたfiducial argumentと呼ばれる推論について検討し,フィッシャーがなぜこのような議論を立てたかについて報告したい.
シンポジウムに関するお問い合わせは,PaSTA 研究員の佐野勝彦、または、狩野裕 氏(kano at sigmath.es.osaka-u.ac.jp)までお願いします。
The symposium is financially supported by The COE Program entitled "Towards a Center of Excellence for the Study of Humanities in the Age of Globalization" and grant-in-aid for Scientific Research (B) #18300094 from the Japan Society for the Promotion of Science.
関連 URL: http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~kano/research/seminar/06_12ph_prop/index.html

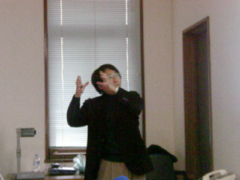







日時:11月18日(土)午後2:00-6:00
会場:京都大学文学部東館4階 COE研究室
オーガナイザー、司会: 大塚淳 氏 (京都大学文学研究科 博士後期課程 哲学専修)
発表母体研究会: 生物学の哲学
講演:
Epigenesisとはゲノムの変異以外のしかたで遺伝子発現に影響が与えられる現象で、遺伝子発現の制御メカニズムとして、あるいは発生学の新展開としても注目されてきています。こうした現象への注目が、生物学の哲学のこれまでの議論の枠組みやトピックにどのようなインパクトをもたらしうるのかについて考えてみます。
現代英米系の心の哲学におけるひとつのアプローチとしての「神経哲学」(Neurophilosphy)は、神経科学的知見を哲学的主張に応用する。一方で科学哲学の一領域として発展している「神経科学の哲学」(Philosophy of Neuroscience)は、神経科学的知見に対する哲学的分析を行う。このようなアプローチの違いは、還元的唯物論や消去的唯物論などの心脳関係に関する立場においても差異を伴う。今回の発表では、両分野の発展の背景、そして両分野における認知と意識に関する研究動向について報告する。
我々は他者の心をどうやって理解しているのか。 近年、ミラー・ニューロンと呼ばれる神経単位についての研究が盛んに行われ、マインドリーディングとの関係が指摘されている。また共感研究に関しても、fMRI(機能的磁気共鳴画像)を用いて一定の成果が得られつつある。本発表では、このミラー・ニューロンについての研究と、fMRIを用いた共感研究を援用しつつ、共感能力とマインドリーディングの関係について考察したい。