安祥寺の概要
安祥寺は、嘉祥元(848)年、仁明天皇女御で文徳天皇の母・藤原順子(809-871)の発願により、入唐僧・恵運(798-869)が開山した真言系の密教寺院である。安祥寺の創建とその概要については、『安祥寺伽藍縁起資財帳』(以下、『資財帳』と略す)と『三代実録』に詳しい。
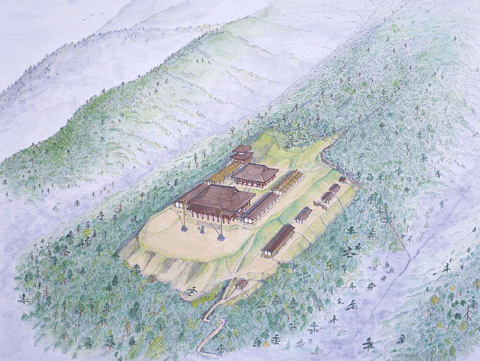
安祥寺上寺想像復原図:本研究会会員の梶川敏夫氏が描いた想像図である。2002年度の測量調査で新たに確認された方形堂については、仮に多宝塔として復原している。あくまで「想像復原」であることをお断りしておく(禁無断転載)
特に、貞観9(867)年に恵運が作成し、現在東寺に伝わる『資財帳』には、伽藍の堂宇・仏像・仏具などの詳細な内容が記されている。それによれば、平安時代の安祥寺は醍醐寺と同様に山上伽藍=上寺と山下伽藍=下寺とから成っていた。上寺には礼仏堂と五大堂とから成る堂院・東西僧房・庫裏・浴堂などの施設が、下寺には約2万平方メートルの寺域内に塔・仏堂・僧坊・門楼などがあったようである。また、安置されていた仏像は現存する五智如来像(現在は京都国立博物館に出陳)・五大虚空蔵菩薩像(現在は東寺観智院蔵)を含めて31体にも及び、多くの仏画・仏具・経典に加えて広大な寺領をも保有していた。
しかし、平安時代前期に大いに繁栄した安祥寺も、平安時代末期以降は衰退に向かったようである。衰退の詳しい経緯は不明だが、上寺は中世には廃絶していた可能性もある。『小右記』永祚元(989)年条によれば、すでにこの時期に上寺へ至る道は相当困難な山道と化していたことがうかがえる。一方下寺は、真言宗小野流三派の一つ安祥寺流(安流)の祖となった宗意(1074-1148)が中興し、その後応仁の乱の兵火によって焼失したと伝えられるが、江戸時代には復興・移転した。現在も山科区(洛東高校西)で法灯を伝えており、江戸時代創建の堂舎が残る。
廃絶した安祥寺上寺は、京都市山科区安祥寺国有林山腹(標高約350m)に遺跡として残っている。遺跡のある丘陵部平坦地に至る道は現在ではなくなっており、人を寄せ付けない。そのせいもあってか遺構の残存状況はいたって良好で、平坦部中央には五大堂・礼仏堂の基壇と思われる高まりが明瞭に見て取れる。元位置に据わったままの礎石がいくつか露出しており、おおまかな伽藍配置も十分に推定可能である。本研究会では、2002年度の冬にこの安祥寺上寺跡を測量調査し、詳細な地形図を作成した。
以上のように、安祥寺は文献・美術・建築・考古といった様々な側面から研究する必要があり、それによって単独分野からのアプローチだけではなしえなかった総合的な研究が可能である。「王権とモニュメント」研究会では、安祥寺に関する研究をメイン・テーマの一つとし、その成果を公表していく。
京都大学大学院文学研究科 「グローバル化時代の多元的人文学の拠点形成」
王権とモニュメント研究会 ouken-hmn@bun.kyoto-u.ac.jp