安祥寺上寺の測量調査
「王権とモニュメント」研究会では、2002年12月20日〜24日、2003年1月11日〜19日の2回にわたって、安祥寺上寺の測量調査を実施しました。京都大学、花園大学、京都府立大学、京都女子大学の教官・学生が参加した大規模な調査で、上寺の全域をカバーする25cm等高線の測量図を作成しました。以下は、その概報です。なお、正式な測量報告については、2004年刊行の『安祥寺の研究 I 』に掲載されています。このコンテンツは、あくまで略報であることをお断りしておきます。
※このサイト上で公開している図面の利用については、メールにてお問い合わせください。
概報・目次
- Appendix 1. 測量参加者一覧
- Appendix 2. 安祥寺測量調査写真集(近日公開予定)
1.測量の方法
本調査の測量図は、縮尺50分の1で、等高線は25cm間隔で作成した。測量の手順は以下の通りである。
(1)基準杭の設定
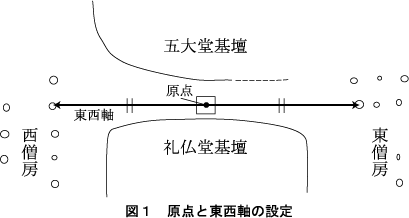 最初に仮の原点を寺域のほぼ中央に設定した。原点は、事前調査において確認されていた東西僧房の礎石を一直線に結び、両者の距離の中点をとることで求めた。同時に東西方向の座標軸についても、この礎石を結んだ直線をそのまま利用した(図1)。
最初に仮の原点を寺域のほぼ中央に設定した。原点は、事前調査において確認されていた東西僧房の礎石を一直線に結び、両者の距離の中点をとることで求めた。同時に東西方向の座標軸についても、この礎石を結んだ直線をそのまま利用した(図1)。
このようにして設定した原点と東西軸を基準として直行する南北軸も設定し、各基準杭はこの座標上に配置した。主要伽藍と東側山腹平坦面との間にある比高差約10mの崖の存在や、調査時間の制限から閉合トラバースによる誤差の配分ができず、開放トラバースによる測量となった。
また、付近に基準となる三角点が存在しなかったため、GPS測量によって国土座標及び標高を得た。ただし、山間地形・生い茂った樹木・電波状況の悪さといった悪条件が重なり、地上波を用いた精度の高いGPS測量を行うことはできなかった。そのため、やむなくGPS単独測位によるデータを用いた。
(2)平板測量
基本的には常時4台の平板を稼働し、地形測量を行った。その際、距離の測定は電子メジャー(レーザー距離計)を用い、より正確な水平距離を求めた。また、事前調査及び今回の調査中に新たに発見した礎石は、露出しているものについては2点以上を平板測量で測定し、そのまま50分の1の縮尺で実測を行った。ピンポールによって位置だけを確認しているものについては、位置のみを測定した。
(3)光波測量
主要伽藍と東側山腹平坦面との間にある崖面については、トータルステーションを用いて数カ所で座標・標高の測定を行い、等高線を作成した。
これらの作業と平行して、寺域全域の雑木等の伐採を行い、地形からも多くの情報を得ることができた。このようにして完成したのが安祥寺上寺跡測量図である。
2.測量の成果
以下、各伽藍ごとに測量調査の概要を述べる。
(1)礼仏堂跡
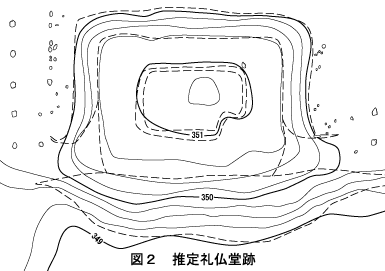 『資財帳』に、
『資財帳』に、禮佛堂一間 長五丈
とある。図2に示すのが推定礼仏堂であり、基壇規模は基底部で東西約21m、南北約15mを測る。残存基壇の高さは、南からは比高差約2m、北からは比高差約1mである。基壇上面には東西約10m、南北約7mのやや高まった部分があって、その周辺に沿って自然石が散在しており、須弥壇の痕跡ではないかと考えられる。
基壇上でのボーリング探査では礎石・根石などが確認できず、建物自体の平面規模は不明である。しかし、北方の五大堂の柱間寸法(10尺又は9尺)を参考に、仮に桁・梁を10尺等間で復元すると、最大で東西7間・南北4間又は5間程度の建物と考えられる。これに関して、基壇南面は明確な段差を持たず、6mほどの長い傾斜地形を呈していることから、その部分に礼堂的な付属屋根を持つような構造であった可能性もある。
なお、基壇南辺の東西両端に、翼状に張り出したスロープ地形が認められる。これは基壇上への登り口と考えられるが、東西僧房の軒廊跡とは位置があわない。これについては僧房の項で詳しく触れる。
(2)礼仏堂跡西側雨落溝跡
長さ南北約10mを確認した。幅は0.6〜0.7m、深さ15cm程度とみられ、地表観察から溝内に石が転落しているのが確認できる。なお、北及び東側の雨落溝は明確には石が確認できず、位置確定はできなかった。南辺は雨落溝の存在そのものが不明である。
(3)東僧房跡と軒廊
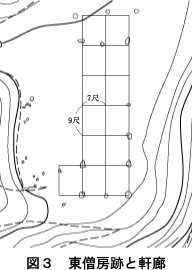 『資財帳』に、
『資財帳』に、僧房二間 一檜皮葺 各長一丈 一板葺 二面有庇 東西軒廊 各二丈 竝檜皮葺
とある。図3にその平面図を示す。基壇は南に段差がある以外は確認できないが、僧房跡の南端と北端の礎石を確認したことから、東西2間・南北6間の建物と判明した。寸法は2間×7尺(2×2.1m)・6間×9尺(6×2.7m)、すなわち4.2m×16.2mで、南北中央と西側礎石のいくつかは確認できなかった。
軒廊は、南面の礎石1カ所を確認し、東西7尺・南北9尺の構造と考えられる。しかし、すでに触れたように、礼仏堂の基壇南端にみられる翼状の張り出しとは位置があわない。図3に見られるとおり、礼仏堂の張り出しが軒廊よりも南に位置しているのである。後世の改作かもしれないが、測量調査だけでは結論は得られない。
この東僧房跡の北側に位置すると考えられる板葺きの東僧房については、ボーリング調査を行ったが礎石等を発見することはできなかった。
(4)西僧房跡と軒廊
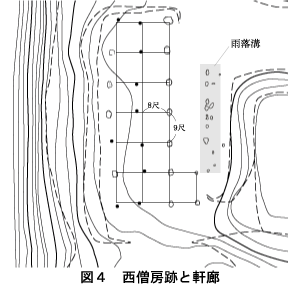 南・西・北の一部で基壇の高まりを残し、南北中央列以外は大半の礎石を確認した。図4がその平面図である。西側は地盤沈下のため、礎石が西に傾いて元位置を移動しているものがみとめられる。建物規模は東西2間・南北6間で、東僧房と同じ構造の建物と判明した。寸法は2間×8尺(2×2.4m)・6間×9尺(6×2.7m)、すなわち4.8m×16.2mである。建物南北柱間寸法は9尺で東僧房と同じであるが、東西柱間寸法は8尺で、東僧房よりも1尺大きくなっている。
南・西・北の一部で基壇の高まりを残し、南北中央列以外は大半の礎石を確認した。図4がその平面図である。西側は地盤沈下のため、礎石が西に傾いて元位置を移動しているものがみとめられる。建物規模は東西2間・南北6間で、東僧房と同じ構造の建物と判明した。寸法は2間×8尺(2×2.4m)・6間×9尺(6×2.7m)、すなわち4.8m×16.2mである。建物南北柱間寸法は9尺で東僧房と同じであるが、東西柱間寸法は8尺で、東僧房よりも1尺大きくなっている。
軒廊の礎石は南北両面を確認し、東西8尺・南北9尺の規模を持つことが判明した。この軒廊の位置についても、東僧房と同様に礼仏堂の基壇南側張り出しとは位置があわない。礼仏堂張り出しが軒廊よりも南に位置している点も東僧房とまったく同じである。
この西僧房跡の北側に位置すると考えられる板葺きの東僧房については、ボーリング調査を行ったが、西側と同様に礎石等を発見することはできなかった。
(5)五大堂跡
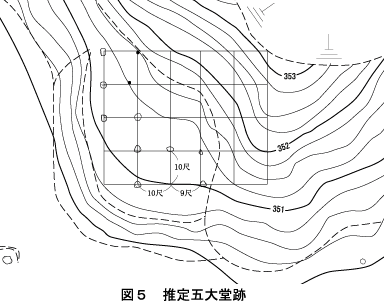 『資財帳』に、
『資財帳』に、五大堂一間 長四丈
とある。図5がその平面図である。元位置で礎石を8カ所確認した。ただし、南面西から2番目は元位置から動いている可能性もある。建物規模は、確認した礎石から判断して東西5間・南北4間とみられる。寸法は東西5間が10尺・10尺・9尺・10尺・10尺、南北4間が10尺等間であるから、14.7m×12mと復元できるが、礎石間の精査により若干の変わる可能性がある。
現在、基壇の東側が土で埋もれている状態である。これは、伽藍の背後から東へ落ちるL字形の谷筋から豪雨などによって土砂があふれて堆積したものと考えられる。この谷筋は、当初背後の山から境内へ侵入する雨水や土砂を防ぐ水切り溝であったのが、時間の経過とともに浸食が進み、現在の地形にみられるように五大堂基壇の東北隅の礎石近辺まで浸食が及んだものであろう。すなわち、中世以降に山城等への転用のため地形改変をおこなった事実はないものと考えられる。
(6)方形堂跡
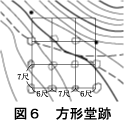 五大堂跡から西北西約11mのところにある建物跡で、今回の調査によって新たに発見された。図6がその平面図である。1981年の京都国立博物館調査(八賀晋氏による測量)においても西南隅の礎石1個が実測されている。
五大堂跡から西北西約11mのところにある建物跡で、今回の調査によって新たに発見された。図6がその平面図である。1981年の京都国立博物館調査(八賀晋氏による測量)においても西南隅の礎石1個が実測されている。
この建物跡の明確な基壇は地表からは確認できないが、礎石のボーリング調査などによって方三間の建物であることが判明した。寸法は東西3間が6尺・7尺・6尺、南北3間が7尺等間であるから、5.7m×6.3mと復元できる。なお、発見された礎石は他の建物跡に比べても大きく、1辺が80cm前後になるものもある。ただし、後世の地盤沈下等の影響か礎石の不等沈下が著しく、礎石間で40cm近い比高差がある。
現在、背後の山腹斜面がずり落ちて、北西から南東にかけての半分以上が埋没している。逆に言えば、本来の寺域平面ははもう少し広かったことになる。これは、五大堂跡の項でも触れた。なお建物の性格は不明であるが『資財帳』に記載されていない、後世に造営された建物と考えるのが無難であろう。
(7)東側山腹平坦地
繁茂した笹などを伐採した結果、主要伽藍から東へ10m下がった場所に、南北に細長い平坦地が存在することが明らかとなった。現在は西側が埋まり東側(谷側)が削られた東下がりの地形になっており、幅5〜7m、南北75mほどの規模である。中央やや南方で石を一個発見したが、元位置を動いているとみられる。他に建物跡を示す礎石らしきものを発見できなかったことから、この石は上方の主要伽藍の礎石が転落したものである可能性がある。
平坦地南端は通路状に狭くなり、そこから南東へ一段下がったところに小規模な平坦地(8×3m程度)がある。また、この小規模平坦地の西側(主要伽藍東僧房跡の南南東)には、山腹平坦地と主要伽藍を結ぶ通路と考えられるスロープ状の地形を確認した。この場所からさらに南南東に下がるスロープ状の地形がわずかに残る部分もあり、谷下から上寺へのアクセスルートのひとつとも考えられる。
Appendix. 1 測量参加者一覧
調査指導
- 梶川敏夫(京都市埋蔵文化財調査センター)
- 上原真人(京都大学大学院文学研究科)
- 吉井秀夫(京都大学大学院文学研究科)
- 菱田哲郎(京都府立大学文学部)
- 山田邦和(花園大学文学部)
京都市埋蔵文化財調査センター
堀大輔
奈良文化財研究所
竹内亮
京都大学
徳永誓子、中町美香子、橋本英将、土屋みづほ、中川あや、阿部健太郎、市川創、東村純子、秋山美佳、上原真依、菅野悠太、桑田訓也、堀田直志、向井佑介、丸吉繁一、伊瀬敬之、井上智弘、笹原風花、嶋根真須美、田村朋美、若杉智宏、岩井俊平
花園大学
河野凡洋、成瀬光一、大橋裕子、鎌田久美子、高橋誠二、根本学、目時貴憲、森島一貴、中村智、宮園亜紀子
京都府立大学
金森悠紀子、高田潤一郎、谷口深幸、中津梓、松田美紀、丸茂朋、李隹宝
京都女子大学
渋谷梓、大月直子、中島ゆき、前田諒子、馬渕美由紀、山口由希子
京都大学大学院文学研究科 「グローバル化時代の多元的人文学の拠点形成」
王権とモニュメント研究会 ouken-hmn@bun.kyoto-u.ac.jp