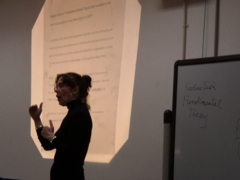


| PaSTA TOP | 趣旨 | メンバー | 研究会案内 | 2004年度の研究会 | Newsletter | COE TOP |

日時:3月20日(日)午後1:00-5:00
会場:京都大学百周年時計台記念館第三会議室
(当初予定されていた陳汎教授の御講演は教授のご都合により中止させていただきます。)
司会 齊藤了文教授(関西大学)
報告者
12月18日(土) 15:00〜18:00
会場:京都大学文学部東館4階COE研究室
Colin Howson 教授(London School of Economics) 'The "Old Evidence" Problem'
Margaret Morrison 教授(University of Toronto) "Emergence in Science"
なお今回の研究会は、「偶然性と確実性に関する哲学史的・理論的研究」研究会(科学研究費補助金研究組織:研究代表 服部裕幸 南山大学教授)との共催になります。
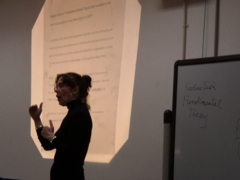


会場: 京都大学文学部東館4階COE研究室
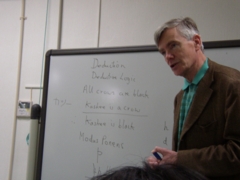
11月27日(土)15:00〜17:00
会場: 文学部新館2F第三演習室 (いつもと会場が違いますのでご注意ください)
Donald Gillies 教授(University College, London) "Probability in Keynes's Economics"
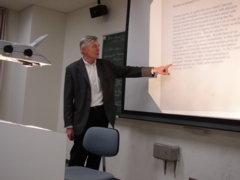
11月20日(土)15:00〜17:00
会場:京大会館211号室 (いつもと会場が違いますのでご注意ください)
Donald Gillies 教授(University College, London) "Bayesianism and Artificial Intelligence"
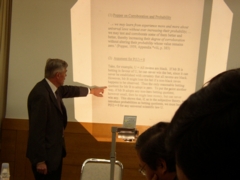
日時:11月11日(木)10:00〜12:00
会場:京都大学文学部東館4階COE研究室
石黒ひで (東京大学大学院総合文化研究科 特任教授) 「ライプニッツの生命論」


日時:10月30日(土)15時〜18時
会場:京都大学文学部新館1F会議室(L111)
神崎宣次 (PaSTA研究会)「その場にいないことについて」
竹中利彦 氏 (明石医療センター附属看護専門学校)「患者のアドヴォカシーと終末期医療」
西川勝 氏 (京都市長寿すこやかセンター研究員)「臨床看護の哲学的転回 ‐臨床哲学と現場‐」
日時:9月24日(金)15時〜18時
会場:京都大学文学部東館4階COE研究室
Bernard Gert 教授 (Dartmouth College) "Moral Arrogance and Moral Theories"
講演のアブストラクトと、当日の配布資料がダウンロードできます。


日時:9月12日(日)14時〜18時
会場:京都大学文学部東館4階COE研究室
寺田俊郎 助教授 (明治学院大学) 「カントのコスモポリタニズム再考」
三谷尚澄 氏 (京都市立看護短期大学) 「カントと「真正な生」:「多元主義的に理解された自律」とは何か?」
司会:水谷雅彦 助教授 (京都大学)
コメンテータ:
舟場保之 助教授(大阪大学)
林芳紀 氏(立命館大学)
佐藤慶太 氏(京都大学)
日時:8月19日(木)午後3:00-5:30
会場:京都大学文学部東館四階COE研究室
Graham Priest 教授 (University of Melbourne) "The Structure of Emptiness"
なお、Priest 教授は八月末で京都大学での滞在期間を終えられるので、公式な研究会へ出席されるのはこれが最後になります。研究会後の懇親会はお見送りパーティとなりますので、夏休み中ですが是非ご参加ください。
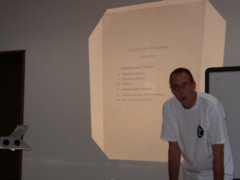


日時:6月26日(土)午後2:30-5:30(午後6:00頃から懇親会があります)
会場:京都大学百周年時計台記念館第三会議室
(当日は英語通訳があります)
コメンテーター:塩谷賢氏
Graham Priest 教授 (University of Melbourne) "Contradiction, Rationality and Belief Change"
中山康雄 教授 (大阪大学) 「信念構造の理論:合理的行為者の信念状態の表示方法」
私たちの信念状態はどのように表示できるのか? 私たちはどのようにして信念を変えるのか? 本発表で、私は、これらの問いに対する私自身のアプローチを説明したい(Nakayama (2001, 2004), 中山(2002))。TBS(信念構造の理論))と TIS(解釈構造の理論)の中心になるのは、二段階評価戦略である。新しい情報を得たなら、この情報は以前の信念構造に取り入れられ、その後、信念体系がこの新しい信念構造から算出される。それから、必要があれば、信念構造が修正される。合理的行為者は、彼の信念体系の整合性を保とうと努める。しかし、彼の信念構造はすべての古い情報を、たとえ、その一部が新しい信念体系に含まれていなくても、保ちうる。信念体系は整合的であるべきだが、信念構造の要素の和は、通常、矛盾を含んでいる。例えば、拒否された信念は、この行為者の信念構造の要素としてなお残っている。この特性は、人類の記憶システムにも共通している。
関連文献




Dr. Koji Tanaka (Macquarie University) "Davidson and Conceptual Scheme"
日時:6月17日(木)午後4:00-
会場:京都大学文学部東館4階COE研究室
日時:5月14日(金)午後3:00-5:00
会場:京都大学文学部東館4階COE研究室
Alex Rosenberg 教授(Duke University)
"Fitness, probability and the principles of natural selection"
I argue that a fashionable interpretation of the theory of natural selection as a statistical or probabilistic claim exclusively about populations is mistaken. The interpretation, wide spread among philosophers of biology, rests on adopting an analysis of fitness as a probabilistic propensity which cannot be substantiated. Moreover, following R. A. Fischer, the interpretation draws parallels to thermodynamics, but these are really without foundation as they misunderstand differences between fitness and entropy. Finally, I show that the population interpretation fails to do justice to the fundamental distinction between drift and selection. This distinction requires a notion of fitness as a pairwise comparison between individuals taken two at a time, and so vitiates the interpretation of the theory as one about populations exclusively.
日時:4月17日(土)午後3:00-6:00
会場:京都大学文学部東館4階COE研究室
Sergio Sismondo 教授(Queen's University) "Epistemics of Computer Simulations"
Because of their novelty, simulations cut across boundaries of pure categories we accept in science, and they are therefore uneasy epistemic objects and tools. What it takes for a simulation to count as representing some object domain needs to be established and re-established field by field. This point generalizes some lessons of the study of experiment of the past twenty years. Simulations, like experiments to seventeenth century inquirers, are rarely transparent representations of a transcendent world. But they can become so by a dialectic that establishes the simultaneous fidelity and productivity of techniques.
現在の研究会については「研究会案内」のページを御覧下さい。