
| PaSTA TOP | 趣旨 | メンバー | 研究会案内 | Newsletter | COE TOP |

●活動報告
「アインシュタインの思考をたどる」講演要旨(内井惣七)
アインシュタインの思考をたどる 特殊相対性から一般相対性へ
日時:3月16日(日)午後1時─5時
会場:芝蘭会館(京大医学部北側)
あいさつ 伊藤 邦武(文学研究科教授)
司会 伊藤 和行(文学研究科助教授)
講演(一)相対的時空と等価原理
講演(二)重力と曲がった時空
内井 惣七(文学研究科教授)
コメンテイター
石垣 壽郎(北海道大学大学院理学研究科教授)
菅野 禮司(大阪市立大学理学部名誉教授)
1. 問題状況 アインシュタインの特殊相対性理論はどういう問題状況の中で出てきたか。力学では「ガリレオの相対性」が成り立つのに対し、マクスウェル-ローレンツの電磁気学ではそれに相当するような相対性が成り立たない。電磁気が伝わる媒質として静止エーテルを想定する説が有力だった(ローレンツ)。
2. 統合への志向 アインシュタイン1905年の論文の冒頭では、「相対運動が同じなら、同じ物理法則が成り立つべきだ」と見なすアインシュタインの基本的姿勢がよく現れている(おそらくマッハからの影響)。この姿勢と見方からすれば、静止エーテルに対する地球の運動が、光(電磁波)の運動を測定しても観測にかからないということは、当然の帰結となるはずである。
3. 二つの原理 かくして、「相対性」と電磁気学の成果を調和させようというアインシュタインの試みは、次の二つの原理を提唱することによって、一挙に解決に向かうこととなる。
相対性原理「自然法則はすべての慣性系で同じ」
光速度一定の原理「光は、真空中を光源の運動と無関係に、また方向に関わりなく、一定速度で伝わる」
アインシュタインは、光速度一定の原理について、「ローレンツの電磁気学で静止エーテル系について成り立つこの原理を借用して、慣性系一般にまで拡張した」という旨のコメントを後年残している(1912年)。
4. 時空の見直し これら二つの原理は、当時の物理学の常識では両立不可能のように見えるのだが、アインシュタインは、「時間と空間の概念を分析し考え直せば、二つは両立する」と論じた。かくして、相対性理論が時空の概念に密接にかかわってくる。その関係で、アインシュタインが古典力学と特殊相対性理論での時空概念の比較を、物理的測定による操作的定義を通して行っているところは興味深い。
5. 古典的時空 運動の記述には、歪まない基準枠(座標系)と、物差しおよび時計が必要。これだけを前提すれば、すべての観測者に共通する絶対的な空間や時間を前提しなくとも、物理学ができる。古典物理学で前提されていたのは、物差しの読みと時計の読み(時刻あわせを含む)が、異なる慣性系の間で共通だということ。
6. 同時性の見直し しかし、特殊相対性理論に移ると、光速度一定の原理の縛りがあるため、離れた場所での二つの(同じ作りの)時計をいかにして時刻あわせするかという問題が出てくる。これが、「同時性の相対性」という帰結をもたらす。しかし、光速についての規約を導入することで、特殊相対性理論でも同時性の規定はきちんと行える。
7. 時空の相対性とローレンツ変換 同時性が決まれば、異なる慣性系におけるそれぞれの時間も時計の読みによって決まるが、同時性の相対性は空間についても違いをもたらす。つまり、相対性は時間だけでなく空間についても広がる。しかし、物差しと時計の読みの相対性は、一様等速運動という相対的運動状態に依存して決まるきちんとしたルールによってつながれている。そのルールが「ローレンツ変換」と呼ばれる関係であり、互いにとって相手の物差しと時計の読みがどのように見えるかがわかる。これは、二つの原理から出てくる。ローレンツ変換のエッセンスは、(パワーポイントの)図にまとめておいた。
8. 力学と電磁気学の調和 このように時空の概念と異なる慣性系の間での変換規則を組み直すことで、古典力学が改訂される。最も目立った改訂は、速度の合成規則であり、古典力学では単純な速度の足し算を前提していたので、この前提のもとではアインシュタインの二原理が両立しないように見えたのである。他方、電磁気学については、「静止エーテル系」という特権的な系を前提する必要がなくなる。電磁気学の法則は、すべての慣性系で成り立つことになり、相対性原理が満たされる。それに伴って、エーテルそのものの想定が不要となってくる。以上が、1905年の特殊相対性理論がもたらした主要な成果である。
9. ミンコフスキ時空 特殊相対性理論は、その後、ミンコフスキ空間において幾何学的にきわめて簡明に表現できることが明らかになった。「幾何学的」と言ったが、これは、通常の空間だけの幾何学ではなく、時間も考慮に入れた幾何学であり、ローレンツ変換で出てくる時空の相互依存がきわめてわかりやすく表現できるものである。
10. 幾何学とメトリック ミンコフスキ空間を二次元と三次元の場合について図で解説するが、肝要な点は、座標系だけ見ていても「幾何学」はわからないということ。その座標系で、二点の座標の値が二点間の「間隔」とどのように関係づけられるかを決める「計量、メトリック」が入って初めて、座標系が量的な、あるいは物理的な記述と橋渡しされるということ。特殊相対性理論を特徴づける幾何学は、ローレンツのメトリックによって特徴づけられる「ローレンツ幾何学」である。メトリックの役割は、一般相対性理論に入るとさらに大きくなるので記憶しておかれたい。
11. 特殊相対論の不備 ここまでで、特殊相対性理論の基本的な考え方を説明した。しかし、特殊相対性理論は、慣性系のみに限定されており、加速系にまで相対性原理を拡張できていないので不十分だとアインシュタインは考えた。すなわち、慣性系と、加速系とでは、成り立つ法則が異なるように見えるのである。もう一つ、不十分である理由は、ニュートンが万有引力の法則で扱った重力が考慮の外におかれている点である。光速度一定の原理により、光速が因果作用の伝播する極限の速度となって、遠隔作用は認めにくいので、アインシュタインは近接作用で重力が作用すると見なす立場から出発する。電磁場と同じように、重力も「重力場」という場を通じて働くと見ればどうなるだろうか。
12. 等価原理の着想 こういった考察は、1907年に新しいヒラメキを得て、ある程度進展を見せる。それが「等価原理」の着想であり、アインシュタインみずからによって「わが生涯の最もすばらしい考え」と呼ばれている。それは、「重力場での自由落下の状態は、力のはたらかない慣性系に等しい」という考え方。ということは、ある観測者にとって重力場があるかないかということは、その観測者の運動状態に依存すると言い換えることもできる。そこで、アインシュタインは、重力場も相対性の網にかかると考えた。また、地上に静止した者から見れば自由落下は一様加速運動であるから、一様重力場におかれているということと、適当な観測者から見た一様加速運動とは等しいという観点も開ける。これが「等価原理」と呼ばれ、一般相対性理論の形成過程で重要な役割を果たす指導原理となる。
13. 慣性質量と重力質量 アインシュタインの研究を突き動かしている一つの大きな動機は、一見異なるものを同じ原理で統一するという志向であるが、等価原理は、慣性質量と重力質量の統一をもたらす。そこで、慣性質量と重力質量の違いを簡単に説明しておく。ニュートン力学に即していえば、慣性質量は運動の第二法則(運動方程式)に現れる「動かしにくさ」「運動に対する抵抗」と理解できる。これに対し、重力質量は万有引力の法則に現れ、卑近な言葉で言えば「重さ」に相当する。そして、経験的な事実としては、「動かしにくさ」は「重さ」と正確に比例しているのである。これは一体なぜだろうか?二種の質量が実は同一のもであれば、この疑問には答える必要がなくなるのである。
14. 等価原理の使い方 等価原理の(初期の)使い方と、この原理を認めればなぜ慣性系と加速系での「法則の違い」が解消できるとアインシュタインが考えたのか、を解説しておく。第一の例は、慣性系において一様加速運動をするエレベーターの例で、慣性系の観測者と、エレベーター内の観測者の記述は一見異なるが、実は物理的に同等だというもの。すなわち、慣性系から見れば「一様加速運動」と第二法則に従った力となるものが、エレベーター内の観測者から見れば、「一様重力場内での静止」と重力になる。これを応用した第二の例では、地上(慣性系)から見た列車の加速(減速)運動で生じた力が、列車から見て生じた重力場による「重力」と等価となって、二つの系の違いが解消される(それゆえ、同じ法則に従う)と見なされる。もっとも、かなり長い期間にわたって、アインシュタインには「異なる運動状態にある物理系」と「異なる座標系」とを同一視する傾向があり、これが後に述べる「一般相対性原理」についてのアインシュタインの概念的混同を招く原因となっているかもしれない。等価原理は相対的に加速する二つの物理系の等価性をいう。ところが、後に触れる一般共変性は、二つの異なる座標系での記述の等価性にかかわる。
15. 新しい重力理論へ それはともかくとして、等価原理と特殊相対性理論を組み合わせることにより、アインシュタインは、1907年から1911年にかけて、「新しい重力理論」に向けてかなりの進展を成し遂げることができた。これを以下に解説しておく。まず、特殊相対性理論を使って加速系を扱うにはどうすればよいのだろうか?それには、加速運動の小さな一部を等速運動の慣性系(特殊相対性が成り立つ「局所ローレンツ系」)で近似させていくという手法がとられる。そして、この加速運動の結果を重力場での結果に読み替えるというのが、アインシュタインの戦略である。この読み替えに等価原理が使われる。この方策を図を使って解説するが、忘れてならないのは、「速度が変われば同時性の条件が変わる」という点である。かくして、一様加速運動を扱うためにさえ、つなぎの局所ローレンツ系が多数必要となってくる。また、慣性系から見れば、一様加速系の時間軸は「曲がった」ものとなる。これも、ミンコフスキ時空で再構成した方がわかりやすい。
16. 一般相対性の発想 そこで、ここから一般相対性への道のりを予告し、その文脈で等価原理の後知恵に基づいた再構成を提示しておこう。1912年以後アインシュタインが目指すのは、「曲がった」座標系と「まっすぐな」座標系の間の行き来を自由にすること、およびその行き来に伴って「重力法則が変わらない」ことを保証することの二点となる。この大筋に即していうなら、一様加速運動に適用された等価原理は、「まっすぐな」座標系と「曲がった」座標系をつなぎ、どちらの重力法則も物理的に等価であることを述べたものである。直観的に図示した方がわかりやすい(図)。この図のうちに、一般相対性の基本的な発想がつまっている。
17. 重力理論の新しい成果 では最後に、1911年までにアインシュタインが重力についての初期の考察で得た結果を紹介しておく。(1)重力場での光の湾曲、(2)重力場での時計の振る舞い(時間の伸び縮み)、(3)重力場でのスペクトル赤方偏移、および(4)重力場での光速の変化。光の湾曲と光速の変化とは表裏一体なのである。
18. 回転系の考察 第一部の最後で示唆したように、重力を扱うためには「曲がった」座標系が必要らしいことにアインシュタインは気づき始めた。1911年プラハに移ったアインシュタインは、壁にぶち当たり、重力を扱うための新しい数学(幾何学)を模索する。おそらく、彼は、重力場を記述するためにはユークリッド幾何学もローレンツ幾何学もダメだと認識したはずである。1912年8月、チューリヒに帰った彼は、旧友グロスマンの助けを借りて微分幾何学の勉強を始めた。転機となったのは、おそらく、回転する円盤の考察だろうと考えられている。この例は、アインシュタイン自身の記述で何度も出てくる。
19. 空間も曲がる この例のポイントは、回転する円盤上では、時間だけでなく「空間も曲がる」というところにある(円周上で物差しが縮み、円周率がπより大きくなるので、非ユークリッド幾何学)。アインシュタインは、1907年の段階ですでに「時間が曲がる」ことに気づいていた。しかし、一様重力場では空間は「まっすぐ」である。そこで、彼は太陽や地球の周りのような、時間的に変化しない静的重力場においても空間はまっすぐだという偏見にとらわれていた。その証拠に、1911年に太陽の近くでの光線の湾曲を計算した時にも、空間はまっすぐだと仮定したので誤った値を得ていたのである。これが修正されるのは、実に1915年の11月、重力場の方程式の完成直前の時期である。
20. 自由なガウス座標とメトリック さて、アインシュタインがここまでに得た見当では、重力場を扱うには加速系で代理させればよく、加速系はどうやら曲がった座標系(以下では「ガウス座標」と呼ぶ)で扱う必要があるらしいということだった。グロスマンに調べてもらってわかったのは、自由で曲がった座標系による幾何学の研究は、ガウスの曲面論に発し、リーマンらが展開した「微分幾何学」においてすでにかなり行われていたということ。そこで、曲がった時空を扱うためには、この微分幾何学をマスターする必要があった。ここでは、最も易しいガウスの曲面論をもとにして、微分幾何学の基本的な特徴を解説し、そこからのアナロジーで重力場の扱い方を示唆する。最も大切なポイントは、ミンコフスキ空間のところでも触れたように、座標の値から幾何学的な量に移行する際に、簡単なピタゴラスの定理ではなく、もっと複雑なメトリックの式が仲立ちとなるということ。このメトリックが、重力場の記述に必要であり、ひいては時空の構造を決めるファクターになるということである。ついでに言えば、「曲がる」とは、部分部分で寸法が変わるということだと理解すればよい。逆に、経験的に時空の構造を知るためには、適当な規約のもとで時間と空間の測定を行っていけばよい。ただし、ミンコフスキ時空の場合よりもはるかに複雑となる。
21. 内在的幾何学 例えば、曲面の曲がり方を、その曲面内の測定で知ることができるだろうか?答えはイエスである。一般に、曲面にそった曲線のうちで最短のものを「測地線」と呼ぶ(ユークリッド幾何学の直線はその特別な場合)が、これも測定でわかるし、面の曲がり方、曲率も寸法の測定によってわかる。このようにして、曲面に内在的な見地から曲率を測り、その曲面の幾何学的性質を決めることができる。ガウスからリーマンらによって展開された微分幾何学は、このような手法を用いる。もちろん、曲面や曲がり方を扱うには、それを高次のユークリッド空間に埋め込んで扱うこともでき、曲率を直観的にわかりやすく「見る」ためには、こちらのやり方が便利な場合もある。しかし、現実の物理的時空を扱う場合、それを埋め込むべき高次の「空間」の想定にはいかなる経験的根拠もないので、内在的な手法による幾何学の方が望ましいはずである。
22. 座標系に依存しない構造 そして、ここで注意すべきことは、このような内在的な手法をとり、自由な「曲がった」座標系をとっても、幾何学的な構造は座標系に依存しない形で取り出せるということである。ガウスが二次元の曲面について示したことを、リーマンは多次元の空間にまで一般化した。例えば、二次元の曲面の曲率は、座標系の選び方に依存しない「不変量」となる。わかりやすく言えば、まっすぐな平面と球面とは種類が違い、その違いは絶対的な区別として取り出せる。そして、その違いは最終的には計量(メトリック)によって記述できる。したがって、ガウスやリーマンの意味で「ある空間が曲がっている」と言われるとき、これは「何々に相対的に曲がっている」という意味ではなく、絶対的な意味、不変量にかかわる違いを意味している。
23. 不変量と一般共変性 そこで、アインシュタインが目指したのは、このような自由な座標系の選び方によって記述しうる不変構造として、重力場を捉えようということだった。むずかしい専門用語では、重力の法則は「一般共変な、重力場の方程式」によって表されると言われるが、この「一般共変性」というのが、「重力の法則は座標系の選び方に依存せず、同じままである」ということを保証する条件である。そして、この方程式の中に現れてくるメトリックが、最終的には時空の幾何学的構造を決めるものとなる。「重力場の方程式を解く」というのは、簡単に言えば、このメトリックを求めることに相当するわけである。しかし、アインシュタインの優れた頭脳と大変な努力にもかかわらず、一般共変な重力場の方程式にたどり着くには、まだ幾つかの障壁が控えていた。
24. 静的重力場についての思い違い 一つの障壁は、すでに触れた「静的重力場」に関するアインシュタインの偏見、思いこみだった。それは、アインシュタインとグロスマンの共著論文(1913年)「一般相対性理論および重力理論の草稿」からもわかる。アインシュタインが1911年の論文で太陽の近くでの光の湾曲を計算したときに、この偏見のため誤った数値が出されたことには、すでに触れた。ちょうどこのケースのように、星の周りにできる重力場は、時間的な変動がなく、同じままで存続する場合には「静的重力場」と呼ばれるが、アインシュタインは静的重力場では時間は曲がっても空間はまっすぐのままだと考えていた。これが彼の思いこみであり、それは回転円盤系では空間が曲がるという洞察を得た後でも継続していたわけである。完成した一般相対性理論(重力場方程式のシュヴァルツシルトの解)によれば、星の周りでは空間も曲がる。すなわち、遠くから星に近づけば近づくほど、星の半径方向の空間的距離は伸びていく。これを直観的に図示するためには、その「曲がり方」を三次元のユークリッド空間に埋め込んだ「埋め込みダイヤグラム」が便利である(ただし、これは便法にすぎない)。ポイントは、座標の値と、距離のような物理的量との間の関係が「非ユークリッド的」になるということで、座標の位置によって物差しの長さが変わると理解してもらってもよい。ついでに言えば、星の内部(例えば地球の内部)では、曲がり方がまた異なるのである。二次元の平面に限って言えば、星の外部は放物線状に、星の内部は球面状に、空間が曲がる。地球を貫通する穴を穿ったとして、この中に小さな球を、時間をおいて二つ落とせばどうなるかという思考実験をしてみればよい。地球は回転せず、内部の密度は一定で、二つの球は衝突しないと仮定する。
25. 座標変換の具体例 この身近な例で、ついでに一般共変性のポイントも具体的に示すことができる。このケースでは、時間と一方向の距離の二次元座標があれば運動が記述できるが、地表に固定した直交座標、黒い球Aに固定した座標、赤い球Bに固定した座標のどれをとってもよい。いずれにおいても、地球内部の曲がり方、曲率は同じ、一つの不変量となって再現される。実は、この曲がり方によって地球内部の重力場が記述されるわけである。三つの座標系は、互いの間で、切れ目のない連続的な変形によって移行することができる。このような移行を、むずかしい専門用語では「微分同相な」座標変換というが、それによって曲率や法則が変わらないことを一般共変性というわけである。(もっと詳しいことは菅野先生が補ってくださるかもしれない。)重力場を記述するメトリックは座標ごとに変わるかもしれないが、記述された物理的内容は同じままに保たれる。
26. アインシュタインの目標 以上、アインシュタインの思考を少々先走って述べたのは、彼が目指そうとした目標を知っておいた方が話がわかりやすいからである。その目標をまとめておくと、(1)等価原理を使うことにより、加速系の考察から重力法則にたどりつけそうだということ、
(2)重力場の記述には一般的なガウス座標を使わなければならず、慣性系のような特権的な系は前提できないこと、そして(3)ガウス座標を使っても座標系に依存しない不変量が幾つかあるので、重力法則も座標に依存しない形で表現しうる、という三点ほどにまとめられる。アインシュタインとグロスマンの「草稿」はそれを目指し、いい線まで行っていたのだが、アインシュタインの静的重力場に関する思い違いがあったため、一般共変な方程式にはたどり着けなかったのである。
27. 穴の議論 さらに悪いことに、この「草稿」直後から、アインシュタインは「重力法則は一般共変な方程式では表現できない」という議論で自他を納得させようとして、ほぼ二年を費やしてしまう。これが「穴の議論」と呼ばれるもので、一般共変性を満たすと重力場の一義性が失われ、重力についての決定論的な法則が成り立たないという論証である(最も周到な議論は1914年の論文)。この議論を簡単な図を使って解説する。ニュートン力学でのわかりやすい例から出発するなら、一定の質量をもつ星が与えられたなら、他の物体がないものとすれば、星の周りの重力場は一義的に決まるはず。そして、この一義性は、当然、物質のない、星の外部の空間にも及ぶ。同じように、アインシュタインの構想する重力理論においても、重力源になる物質が与えられたなら、その周りの空っぽの空間でも重力場は一義的に決まるはずである。ところが、アインシュタインはこの予想を覆す議論が一般共変性を介して成り立つと論じた。
28. 重力法則は一般共変ではあり得ない? まず、一般共変な方程式で重力法則が書けたとしよう。つぎに、適当な条件が与えられたとき、物質のない領域を「穴」と呼ぶことにし、この穴の中を一つの測地線(重力場の中での最もまっすぐな経路)が通っているとしよう。これは、適当な座標系Kを選んだとき、一般共変な方程式の解として得られたメトリックG(x)──第一の解──によって決まる。ところが、一般共変性によれば座標系を変えてもよいので、穴の外ではKとまったく同じだが、穴の中ではKと異なり、しかも穴の境界ではもとの座標系とスムーズにつながるような別の座標系K'(座標変換)を考えると、この新しいK'においては、もとの解はG'(x')に変換され、穴の中での測地線の経路はKにおける経路とは違うはずである。ここまでは何の問題もない。しかし、一般共変性によれば、このx'にもとのxを代入してもとの座標系に再び戻せば、得られたG'(x)はもとの座標系での第二の解となる。GとG'は穴の中では当然異なるので、かくして、もとの同じ座標系において二つの異なる解が得られ、それぞれに従う測地線は(穴の中では)違う経路をとって、重力場の一義性が失われるではないか!これは、アインシュタインが考える重力理論の要件を満たさない(決定論が崩れる)ので、重力法則については一般共変性をあきらめなければならない、とアインシュタインは論じた。
29. 数学的座標と物理的時空 この議論、どこがおかしかったのだろうか?後知恵によれば簡単かもしれないが、アインシュタインにして、この議論を克服するために二年かかったのである。アインシュタインの先入見は、おそらく、「座標系を与えればそれによって物理的時空がある程度記述されている」、あるいは「重力場を与える前にすでに物理的時空が成立している」というものではなかっただろうか。「穴の中で異なる測地線が二つ以上できて困る」という考えには、メトリックG(x) あるいはG'(x)が与えられる以前に、物理的時空の異なる点が二つあって、それぞれのメトリックが違う点を拾い出すので一義性が失われて困るという前提があったはずである。しかし、アインシュタインがたどり着いた解決策は、「二つの座標系は数学的に異なり、したがって二つのメトリックも数学的には異なるが、物理的時空を考える際には、数学的な同一性の基準とは違う基準が適用されなければならない」というものだった。つまり、物理的な時空点を拾い出すためには、座標系プラス、重力場を表すメトリックと、セットにして考えなければならず、一般共変性によってそれらがつながるからには、それらは数学的には異なっても、物理的には同一の事態を表していると見なすべきだということなのである。要するに、一般共変性によって互いに変換される解は、数学的には異なるが物理的には同一である。重力場が記述できる以前には、物理的時空については語ることができないのである。これは、ニュートンの絶対的時空に反対したライプニッツに近い考え方である。この考え方にたどり着き、1915年の11月にアインシュタインはそれまでの偏見を克服して、重力場の方程式を一気に完成した。これには、もちろん、水星の近日点移動の謎が一般相対性により解決できることと、太陽の周りでの光の湾曲についての新しい予測(1911年の予測の二倍の量となる)という副産物も伴っていた。
30. 穴の議論から学べること 以上の顛末を踏まえて、われわれの後知恵を活用するなら、次の四点が指摘できるように思われる。
(1)ガウス座標は時空記述の単なる数学的形式であり、それ自体では物理的意味を持たない。
(2)一般共変性は、ある物理的記述が座標系を変えても同じ物理的内容を維持できるための数学的条件である。
(3)この一般共変性により、重力場の記述を座標変換によって変えても、物理的内容は変わらない。
(4)物理的時空は、重力場を表すメトリックが与えられて初めて成立する。
31. 一般相対性原理の多義性 ただし、アインシュタイン自身が、一般相対性理論完成の時点で、これら四点をはっきりと自覚していたわけではなさそうである。(1)と(4)についてははっきりと自覚していたことの証拠は多いが、他についてはまだ混乱が残っていたふしがある。それがよくわかるのは、ほかならぬ「一般相対性原理」の定式化と説明の箇所である。例えば、「一般相対性理論の基礎」という1916年の総説論文では、
(a)「どのような座標系においても成り立つ方程式」
という一般共変性の条件を満たせば、
(b)「どのような運動状態にある系も、法則の定式化に関しては同等である」
という条件──これが「一般相対性の要請、あるいは原理」と呼ばれる──も満たされる、と主張されている。ところが、これら二つの条件は違うはずである。(a)において言及されているのは「座標系」であるのに対し、(b)で言及されているのは運動している物理系である。そこで、物理系に言及する一般相対性原理が、数学的条件である一般共変性だけから出てくるわけがない。ここにはアインシュタインの混同があり、事実、翌年に数学者の E. Kretschmann がこれを指摘している。
32. 一般共変性と物理的内容 この点を手っ取り早く理解するためには、慣性系と一様加速系という、運動状態の異なる二つの物理系を考えてみればよい。これは等価原理のところでも出てきた対比だが、アインシュタインの混同を見るためには有益な事例である。端的に言えば、慣性系に重力場はなく、一様加速系には重力場があるので、二つは物理的に等価ではない。「重力場のある慣性系」という表現のもとで、アインシュタインは「まっすぐな座標系で重力を記述する」ということをおそらく意味したのであろうが、そこが混同の始まりである。「まっすぐな座標系」には物理的内容はないのに対し、「慣性系」には一定の物理的内容がある。それゆえ、慣性系に言及する特殊相対性原理には物理的内容があったわけである。一般相対性がこれの拡張を目指すなら、当然物理的内容をもたなければならない。しかし、一般共変性には物理的内容がなく、そのような内容は外から補わなければならないのである。
33. 一般共変性は一般相対論のエッセンスではない 一般共変性が、アインシュタインの考えていたような「一般相対性」とは違うことを納得するためには、ユークリッド幾何学、ニュートン力学、あるいは特殊相対性理論についてさえ、一般共変な定式化ができることを理解しさえすればよい。物理的幾何学と理解されたユークリッド幾何学が、座標系の選び方に依存しない形で定式化できることは、微分幾何学での常識である。これは、二点間の空間的距離を不変量にするようにすれば、まっすぐであろうが曲がりくねった座標系であろうが、同じ内容を記述できる。空間の曲率はゼロ、つまり、まっすぐな幾何学である。幾つかの図で解説。
34. アインシュタインにも相対性の誤り 以上のような概念的混同があったからといって、アインシュタインの一般相対性理論の値打ちが損なわれることはいささかもない。ただ、アインシュタインの権威を借りて誤った哲学的議論の根拠としないように、物理学者や科学哲学者が注意すればよいことである。
第一部 相対的時空と等価原理
1.エーテルは,光の波動説のもとで光の伝播を担う物質として想定され,その中を運動する物体に部分的に引きずられると見なされていた.このように,エーテルが動くことを認めると,Einsteinが原理とした相対運動も,エーテルとの間の相対運動という観点が出てくるはずである.したがって,Einsteinは初めからエーテルの存在を認めずに,エーテル以外の物体の間の相対運動を考えようとしたということになるであろう.電磁波という波動を認めながら,それを担う物質を否定するという考えは,当時としてはきわめて異端であったであろう.特殊相対性理論の革新性は,時間と空間について,同時性や同所性を相対化したことだけではなくて,空間あるいは時空を物体の運動に対して中立的な存在から,物体に影響を及ぼす性質を持ちうる存在,波動の伝播を担う存在に変えたこと,つまり空間あるいは時空を物質化したことにあったと思われる.
2.等価原理は2重の意味で用いられる.まず,重力場が存在し,この重力場内で静止している座標系K を考える.そのためには,このK は重力場を打ち消す力で支えられていなければならない.このときK は慣性系となり,K から眺めた物体の運動は,重力の作用のもとで運動法則に従う運動となる.他方,重力場のないところで,慣性系から見て一様な加速運動をする座標系K' を考える.K' から眺めた物体の運動は,あたかもK' が,K と同じように,一様な重力場内で静止しているかのように生じる.このとき,等価原理は,K とK' を物理的に同等と見なす,と主張する原理であるとされる.上記のK が置かれている事態と,K' が置かれている事態は客観的に異なっているが,これら2つの異なる事態を物理的には区別できない,あるいは,区別できないものとして扱う,という説明がなされる.ということは,K が表している事態をK' から眺めているかのように表してもいい,と言われる.例として,K' における光の振舞いから,K における光の屈曲が結論される.
もう1つの意味は,K' においても実際に重力場が存在している,と物理学は考える,という意味である.そうすると,等価原理は,2つの異なった事態が物理的に等価である(同等である)という意味ではなくて,単一の物理的事態があり,その表現として(局所的には)重力場による表現と加速運動による表現という,同じように正当な表現がある,という意味に解されることになる.2つの物理的に区別できない事態があるのではなくて,1つの事態に同じように正当な2つの表現がある,という意味である.それでは,これらで表現される1つの事態は何か,と言うと,その事態は,座標系を設定して成分表示する前の計量テンソルそのものによって表される,ということになる.
第二部 重力と曲がった時空
3.一般相対性理論における「穴の議論」から次のような考えが導かれる.微分可能多様体M を基礎に採る数学的定式化では, (M, g, T) が1つの物理的世界に対応していると考えると決定論が成立しないという結論が導かれる.したがって,決定論を維持するためには,(M, T) を共有する微分同相な族{(M, g, T)} が1つの物理的世界に対応していると見なさなければならない.したがって,p∈Mは物理的な時空点に一意に対応するとは限らない.そこで,物理的世界に一意に対応する数学的定式化を行なうには,微分同相な族{(M, g, T)} の (M, g, T) が共通に持っている性質を直接定式化することが考えられる.このために, (M, g, T) の定式化の途中で現れるC∞ (M)がもつ環の構造に注目して,時空点の集合M を前提せずに,代数としての環R を基本にする定式化が考えられた.しかし,この試みは成功しなかった.R から点集合としてのM が構成され,穴の議論による非決定論が再び結論されるからである.結局のところ,一般相対性理論については,決定論を維持しながら,物理的世界に一意に対応する定式化を与えることができないようである.
第一部 相対的時空と等価原理
1.時間、空間、速度の関係
絶対時空を否定して相対時空を前提にするならば、「時間、長さ、速度の定義」は相互規定的循環論となる。速度を定義するには時間と空間の測り方が決まっていなければならず、時間を決めるには、一定速度の周期運動などを用いるが、その速度が一定であることを知らねばならない。離れた2地点での長さの比較についても同様に、信号速度と伝播時間を知らねばならない。
時間、長さ、速度の3つの中の2つを何かの方法で規定(仮定)すれば、それによって残る1つが定義できる。
アインシュタインは、特殊相対性理論では「光速度一定性」の仮定により、まず速度を規定し、時空については、各慣性系ごとに、一様時間とユークリッド空間を前提として「時間、長さ、速度」の関係を組み立てた。
2.特殊相対性理論の基礎原理
特殊相対性理論は、
運動の相対性、光速度一定性
を基礎原理とし、それを基に運動学と力学が築かれている。
運動学では慣性系間の関係を与えるローレンツ変換(LT)が中心的役割を担う。LTを導く際、「光速度一定性」ばかりでなく、「運動の相対性」すなわち、どちらの系から見ても相対速度の大きさは、同じvと−vとすることが効いている。すべての慣性系で「光速度一定」であれば、時空尺度は慣性系ごとに異なるので、このことは自明ではなく、仮定である。時空尺度とは違い、相対速度に関しては共通なのである。
3.「光速度一定性」の根拠
アインシュタインは如何にしてこの仮定に到達したかは、あまり明らかではない。今から見れば、その論理的根拠は次のようにいえる。
電磁気学のマクスウエル方程式から、電磁波(光)の方程式が導かれ、電磁波の伝播速度はcであることが帰結される。電場Eの真空中の伝播方程式は

となり、磁場Bについても同様。最後の時間微分の項の係数cが光速度を与える。このcは普遍定数である。運動の相対性の仮定から、全ての慣性系は同等であり、マクスウエル方程式が成り立つので、同じ伝播方程式が導かれ、光速度はcとなる。
それゆえ、すべての慣性系は物理的に同等であるという、運動の相対性の仮定と、電磁気学のマクスウエル方程式を前提とすれば、すべての慣性系でマクスウエル方程式が成り立ち、光速度は必然的に同一のcとなる。
「相対性理論は間違っている」という主張をよく見かけるが、その説明に運動の相対性とマクスウエル方程式を前提にしているので論理的に矛盾している。ここで「光速度一定性」の論理的根拠を指摘しておきたい。
4.座標変換に対する理論の不変性
特殊相対性理論では、すべての慣性系は物理的に同等であり、LTにより結ばれる。座標変換の下での理論の不変性(方程式の共変性)は、その理論の客観性を増す。
基礎方程式はその理論の性格(論理性)を表現している。その理論の性格を決めるのは座標変換の下での「不変量」である。
・ニュートン力学では、不変量は「空間距離と時間」:ガリレイ変換
・特殊相対性理論では、不変量は「4次元距離(ミンコフスキー空間の世界線)」:
ロ−レンツ変換。
しかし、慣性系はまだ特殊であり、その選択は人為的である。自然法則は本来、人間の認識の仕方、理論を組み立てる基準系の選び方によらず存在している。それゆえ、より一般的な基準系を基に理論を築くべきである。そこで任意の座標系、一般座標系に進んだ。
・一般相対性理論では、不変量は「4次元リーマン空間の距離」:一般変換
座標変換の下での不変量を決めることで、変換の型が決まり、理論が決まる。この不変量の規定に物理が入る。時間・空間の性質(幾何学的性質、計量)はこの不変量によって規定される。したがって、時空の構造は理論と共にその中で決まる。
5.物理量の数量化
物理量(数量化)が客観的に定義されるためには、次の同値関係と順序関係を満たさねばならない。
同値関係 反射律:a〜a,対称律:a〜b⇒b〜a,推移律:a〜b,b〜c⇒a〜c順序関係 反対称関係:a≧b,b≧a⇒a=b,推移律:a≧b,b≧c⇒a≧c
同値関係の対称律は2人の間での同値関係(どちらから見ても同値)、推移律は3人以上の人の間での同値関係を与えるから、客観的等値を保証する。順序関係についても同様。
以上の条件を充たす物理量は全ての人に普遍的かつ客観的に決められたといえる。たとえば、長さ1mといえばどこででも通用する。
ところが、相対性理論では、互いに相対運動をしている物体間では、慣性系ごとに時空尺度が異なるので、この関係が崩れる。等しい長さの棒の長さでも互いに相手の棒の長さは短く観測されるからである。時間(同時性、遅れなど)についても同様。しかし、一つの慣性系で(に変換して)比較すれば、同値関係と順序関係は満たされる。また、異なる慣性系間の物理量はLTにより一義的に変換される。それゆえ、客観的数量化はでき、矛盾のない理論が組み立てられる。
6.変換群の意義
物理学での座標変換は「群」を作っている。変換に対する「不変量」があるから、それを不変にするすべての変換は一つの変換群に括れる。
群の定義:恒等変換(単位元)、逆変換(逆元)、結合変換(2つの積元)を含む集合。
これらは、同値関係の反射律、対称律、および推移律にそれぞれ対応している。恒等変換はそれ自身への変換であり、逆変換は座標系間の相対性を、結合変換は引き続く2つの変換が1つの変換で表されることを意味する。
変換が群を作ること、すなわち逆変換が存在すること、および、2つの変換の結合が同じ性質の1つの変換で表されることは、すべての座標系が同等であることを保証している。その理由をローレンツ変換群を例にとり説明する。慣性系K1からLT1で第2の慣性系K2に移り、次にK2からLT2で第3の慣性系K3に移ったとすると、K1からK3に直接移る変換も1つのLT3である(その逆変換も)。ここにK1・K2=K3。したがって、どの慣性系からLTで移ってもまた慣性系となる。それゆえ、全ての慣性系が同等であることが保証される。
もしそれらが群をなさなければ、LT1とLT2はLTであっても、LT3は必ずしもLTではないことになり、どの座標系から移ったかにより行き先の座標系が慣性系であるとは限らないことになる。したがって、その場合はすべての慣性系の同等性は失われる。
座標変換が群を作るなら、客観的物理量の定義に必要な条件(同値関係)との対応からして、その変換が客観的意味を有することにもなる。
変換群を用いて、いろいろな特性が導かれる。例えば、LT群から、速度の合成則が導ける。
一般相対性理論でも4次元時空のリーマン空間での線素を不変にする変換は群を作るから、このことは任意変換(ただし微分可能で逆変換が存在)で移る座標系がすべて同等の資格を有することを示す重要なポイントである。
7.電磁場から重力場へ
アインシュタインは特殊相対性理論で電磁気学を完全な形式にし、場の概念を確立した。重力も重力場による近接作用として定式化に向かった。
慣性系は特殊であり、人為的系であるから、一般の基準系で成り立つような理論が望ましい。
また、エネルギーと慣性質量の同等性から、電磁場のエネルギーも重力の源になりうる(等価原理を認めるなら)。すると、電磁場だけでは不十分で、重力場を取り込んだ理論が必要になる。
特殊相対性理論は不完全→一般相対性理論へ。
8.等価原理
慣性質量Miと重力質量Mgの同等性=等価原理が問題になる。
等価原理は、原理的にはガリレイの落下法則(真空中で、すべての物体は重さによらず同一加速度で落下)の中にすでに含まれていた(精度が問題だが)。
すべての物体に対して、

ならば、単位を巧く決めれば、K=1(等価原理)としうる。
もし、等価原理が成り立たなければ、重力による運動現象に矛盾が起こる。なぜならば、質量がMi、Mgの物体の落下で、その物体に仕切(仮想的)を入れ(あるいは実際に割って)mi,mg と mi’,mg’に分けたとする。等価原理が成り立たないなら、
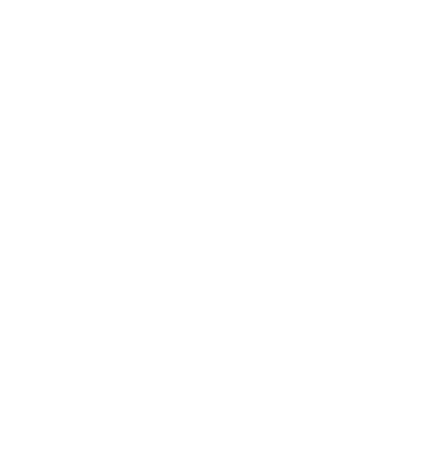 = k, = k,  = k', = k', 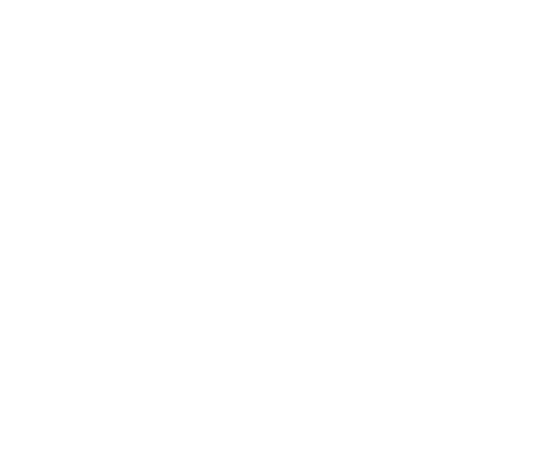 = K = K |
|||
  = K = K |
上式は k≠k’≠K なら矛盾
また、落下加速度は、ニュートンの運動方程式を使うと、(重力をGとする)
 = =  = = 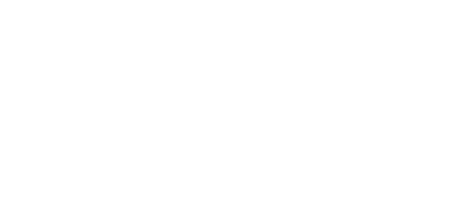 , ,  ' = ' =  = =  , , |
|||
A =  = =  |
となり、物体を一つと見るか、2つと見るかで、加速度が異なり矛盾をきたす。切り方は任意であり、2つ以上何個にも切れる。全ての切り方に対して矛盾のないようにすることは難しい。
よって、 等価原理がないと、矛盾のない力学の定式化は非常に複雑困難になる。あるいは不可能かもしれない。
第2部重力と曲がった時空
9.重力の幾何学化の根拠
質量に関する等価原理は、すべての物体はその質量や化学的性質などによらず重力によって同じ加速度を受ける、つまり、初期条件さえ同じなら全ての物体は同一軌道を運動することを意味する。落下法則は質量の大きさによらず全て同一加速度で落下するから、それを一般化して等価原理を次のように表現しうる:
静止系における一様重力場=無重力の等加速度系
加速度による見かけの力(慣性抗力)=重力
非一様な任意の重力場は、場所ごとに加速度の異なる「局所加速度系」の結合系(曲線 の集合)で表現可能、すなわち曲がった空間で表現される。
∴重力作用の効果は物体の一切の性質に関わりなく発現するから、重力は物体を離れて 空間の構造(性質)に帰すことができる:重力の幾何学化。
10.重力理論は非線形理論
特殊相対性理論のエネルギーと慣性質量の同等性により、電磁場、重力場のエネルギーは慣性質量と同等である。等価原理によりそれは重力質量を生む。したがって、重力場はそれ自身が重力の源となって重力質量に跳ね返ってくる。重力は重力と相互作用する。
よって、重力場は非線形性を持った場であり、重力理論は非線形理論となる。
アインシュタインの重力場の方程式:
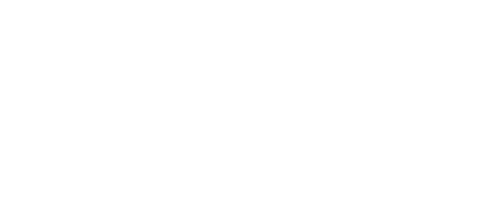 |
(1) |
Rμν はμνにつき対称でリッチのテンソル、Rはスカラー曲率と呼ばれて、ともにリーマン空間の曲率と密接に関係している。 Tμν は物質分布を与えるエネルギー・運動量テンソルである。 Rμν とRは計量テンソルgμνとその1回微分、2回微分のみの非線形関数であり、gμν だけで決まる量である。
左辺は時空間のみで決まる量、右辺は物質(エネルギー・運動量)分布のみで決まる量である。
11.入れ物(時空)と中味(物質)の相互規定性
重力方程式(1)は時空の計量gμνと物質分布Tμνの関係を与える式で、Tμν が決まればgμν が決まり、gμν が決まれば物質分布Tμνが決まる。
時空間の構造はgμνで決まるから、物質の入れ物である時空間と中味の物質分布とは相互に依存して決まり、それらの運動変化も相互依存的である。つまり、時空構造と物質分布は相互規定的関係にあり、両者は持ちつ持たれつの関係で自己運動する1つのシステムである。
時空間の歪みが重力であるから、その時空間の構造によって中の物質が運動し、その物質分布の変化が時空の構造(歪み)に跳ね返って時空が変わる。その時空変化がまた物質の運動に跳ね返る。しかし、この変化過程は、いずれが原因で他方が結果というのでなく、同時的で、どちらも原因でもあり、また結果でもある。つまり、同時的に相互規定に関係にある。
宇宙はそのような自己運動系である。このように時空と物質を不可分な相互前提的存在とし、かつ相互規定的存在様式とする物理学の定式化は、一般相対性理論が最初である。
12.ゲージ不変性と「穴の議論」
重力方程式(1)は10個の方程式を与え、それらは一般変換に対して共変的である。10個の式の中、6個のみが gμν 時間についての2回微分を含み、他の4個は時間の一回微分しか含まない。
(1)式の左辺を纏めて Gμν と書くと(i,j=1,2,3は空間成分、0は時間成分)
Gij=(gijの時間の2回微分、gμν の時間の一回微分、・・)の関数,
Gμ0 =(gμνの時間の一回と空間の一回微分・・)の関数
それゆえ、gμ0 の時間の2回微分はこの方程式に含まれない。
力学では、運動方程式は時間の2回微分の方程式である。これに対して、時間の1回微分の方程式は速度と位置の関係を与える条件式、すなわち、初期条件に対する束縛条件であって、運動方程式ではない(例:ニュートンの運動方程式)。 gμν に対しても同様。
したがって、重力方程式のうち6個のGijのみが本当の運動方程式であり、4個は初期条件に関する束縛条件なのである。すると、重力方程式で運動が決まるのは6個のgij のみであって、gμ0 は決まらない。
10個の計量gμν を決める運動方程式は6個しかないので、計量は一義的には決まらない。4個のgμ0 は任意に選べる。
10個の式が独立な運動方程式でないことは、ビアンキイの恒等式というのがあり、(1)式の左辺の共変微分(絶対微分)は恒等的にゼロになる。その恒等式は4個(4成分)あり、それらはgμνに対する4個の条件式を与えるのである。(1)式の左辺が恒等的にゼロならば、右辺もゼロでなければならない。右辺Tμν の共変微分がゼロであることは、エネルギー・運動量の保存則である。
計量テンソルgμν が一義的に決まらないという、このことが一般共変性を満たす根拠である。つまり、任意関数を含む座標変換を許す理由である。
基礎方程式が運動方程式として全てが独立でなく、束縛条件を含む場合、その方程式系を特異系という。特異系であり、かつ任意変換に対して方程式系が不変なものをゲージ変換に対して不変(ゲージ不変)であるといい、そのような理論をゲージ不変理論(ゲージ理論)という。
重力方程式(1)はゲージ理論であり、4つのゲージ変換の自由度を有している。ゲージ不変な方程式の解は一義的でなく、不定な成分がある。この場合、束縛条件に矛盾しなければ4つのgμ0 は任意に与えることができる。1組の解に対して、ゲージ変換で繋がる全ての解の組は物理的に同等なのである。計量gμν (重力ポテンシャル)そのものには物理的意味はなく、本当の物理的状態を与えるのはその微分である。
これが、アインシュタインが一般相対性理論を築く過程で、陥った誤り、重力理論は一般共変性を充たさないという、いわゆる「穴の議論」に填った理由である(これは後で分かったこと)。当時、彼は計量テンソルは一義的に決まらなければならないと思いこんでいた。
よく知られたゲージ理論は、電磁気のマクスウエル方程式である。電場Eと磁場Bは電磁ポテンシャルAμ(x)の1回微分で表される:
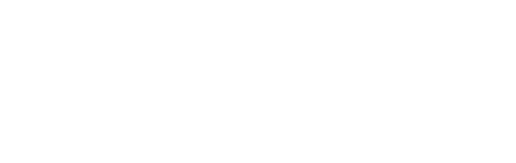
この F
 は任意変換
は任意変換
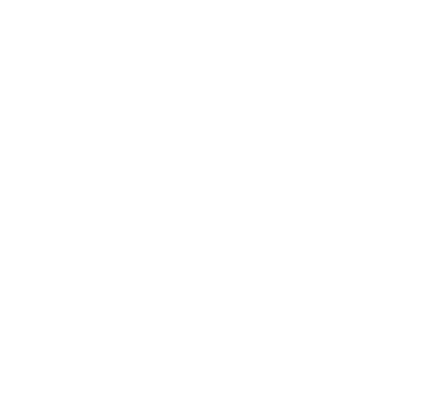 |
: Kはxの任意関数 (2) |
で変わらない。したがって、EとBに関するマクスウエル方程式も不変である。つまり、マクスウエル方程式を解いてポテンシャルAμを求めても、A0 は決まらず任意性がある。物理的に意味のある物理量(観測に掛かる量)はポテンシャルAではなく、電場Eと磁場Bであるから、ゲージ変換(2)で物理的内容は変わらない。
13.真空の物質性
特殊相対性理論は真空のエーテルを追放し、空の空間を電磁波が伝わる「物理的場」としたとよく言われる。しかし、空の空間がどうして物理的場となりうるのか、その疑問に対する答えはなかった。
一般相対性理論では、真空、すなわち物理的空間は「場」であり、電磁場や重力場の担い手として、単なる空虚な空間ではない。空間はその歪みによってエネルギー・運動量を有する存在であるから、物質的存在である。
さらに、場の量子論では、真空の物質性は一層強くなる。特殊相対性理論は真空からエーテルを追放して空にしたが、量子論と結合して真空を粒子・反粒子対で埋め尽くし、真空に物質性を与えた。このような真空は、電磁波を伝える物理的場となりうるだろう。
また、相互作用の統一理論では、真空をヒグス場の縮退した空間(真空の相転移)とした。このように、相対性理論は、真空概念にも革命的変化をもたらした。
真空概念の発展史は、物理学理論の発展史でもある。
14.アインシュタインの統一場
重力場の幾何学化に成功したアインシュタインは、電磁場と重力場を統一して、両者を空間の構造に填め込もうとした。その思想を実現しようと、多くの人たちが試みたが、遂に成功しなかった。その理由の一つに、電磁場には等価原理に当たるものがないことである。
アインシュタインの試みた統一場理論は成功しなかったが、全く異なる方面から、量子場の理論に基ずく基礎的相互作用の「統一理論」が起こり、一部成功した。ワインバーグ・サラムの弱電統一理論がそれである。
重力まで含めた統一理論は非常に難しいが、いずれ成功するであろう。アインシュタインの統一的自然観への思考法は素晴らしいものである。
PaSTA研海外派遣プログラムにより、アムステルダム大学(オランダ)にて一月二十八日より二月十日までの二週間、文献調査およびI. デ・ヨング教授との意見交換を行った。教授はナラトロジーの成果を取り入れた研究で著名な古典学者であり、Narrative in Drama: the Art of the Euripidean Messenger-Speech.(Mnemosyne, Suppl. 116) 1991などの著書がある。また彼女の影響下に、ギリシア劇の翻案研究や、近年の文学理論と古典学の対話を試みる研究などが進められている(J. P. Sullivanとの共編、Modern Critical Theory & Classical Literature, Leiden, 1994)。わたしの関心とディスカッションの中心は、おもにギリシア劇における翻案(adaptation)の性質についてであった。予め提出した英語原稿の小論二編を検討され、二日間の議論の場と調査の便宜を提供してくださった教授に、そしてこのような機会を与えてくれた本研究会に感謝したい。
わたしは、「作品」概念にまつわる「オリジナル」一元論を、主に翻案現象(adaptation)の検討から再考し、それを通じて本研究会の課題「一元性神話の解体」に取りくんでいる。オリジナルを頂点とする序列のなかに翻案を位置づける従来の見方は、わたしには自明であると思われない。それは、作品をわれわれが享受する際の受容の問題圏にとどまらず、作品の存在論的なあり方としても、再検討が迫られているのではないか。また同時に、作品を出発点=オリジンとし、演出や個々の上演が派生するという見方もまた今や自明であるとは思われない。メディアの変換を伴う多様な転用(例えば無数の映画“作品”(film adaptation)や、ドイツの作曲家Zenderによる“作曲された解釈”(Eine komponierte Interpretation)の試みなど)のあり方は、もはや派生という見方にとどまらない、作品と解釈や上演のあたらしい関係を提出しているように思われるからである。
現在、当然のように「作品」として認められているギリシア悲劇作品もまた、制作当初は翻案の性質を帯びていた。それらは、観客の知悉する少数の有名な家系にまつわる伝承や英雄伝説、神話に基づいて繰り返し作られていた。それはいわば、観客の雑多な知識に取材する“オリジナルなき翻案”なのである。詩人は、その中から素材の取捨選択を行い、自らの作品の統一を形成するといえる(cf. アリストテレス『詩学』8章)。これらが「作品」として地位を得るのは、オリジナルを持たないからだろうか。ちがう。例えばエウリピデスの『ヒッポリュトス』を自らのオリジナルとして持つ、ラシーヌの『フェードル』はどうか。
ラシーヌは自ら序文の中で、原作がエウリピデスであることを述べている(ギリシア悲劇は、もはや「作品」となっているが、それが伝説にまで遡ることにも言及していることも見逃せない)。そればかりか、第一幕においては、衰弱する女主人公の台詞をエウリピデス作品から引用している。古代の劇の中で愛欲の女神アプロディテによって恋を吹き込まれたパイドラは、その治療として(相反する貞潔の女神アルテミスのアトリビュートである)馬場や森に憧れる。ラシーヌはその台詞をほとんどそのまま引用するのである。しかし17世紀古典主義の劇の中には、すでに二柱の神は存在せず(漠然とした愛の女神ウェヌスがいるのみ)、ラシーヌの衒学を差し引いても唐突な印象は免れない。この古代の痕跡はエウリピデスの作品を参照することなくしては、意味が理解できない。件の台詞によって、17世紀の翻案は、そこにない古代のオリジナルを指し示そうとしているのである。ラシーヌの劇全体は、近代に大量発生したアンティゴネーたちめぐる劇についてG. スタイナーが主張したように、むしろ恋と政治の相克を扱うものなのである。フェードルが、恋の駆け引きと政治的同盟に二度、敗北を喫せねばならないのもそのためである。たとえば、こんなふうに理解することも出来るだろう。──個人と共同体の相克をめぐる『ル・シッド』論争を経た近代の作家として、ラシーヌは、情念と政治に翻弄されるフェードルを描いた。しかし彼女は成長していくヒロインである。第一幕・二幕での、政治的な和解を装いつつも情念のみに突き動かされる恋一途のフェードルは、いまだ古代のパイドラの面影そのものである。つまり、件の台詞は、近代劇の中に嵌め込まれた古代のイコンの様に機能しているのである。──もちろん、以上の解決は一つの可能性にとどまる。むしろこの可能性から、翻案から作品へと位置づけが変換される問題を、二点みてとりたい。(1)明らかなオリジナルの痕跡、しかもそれがいかに翻案の内部で異質に見えるときも、われわれは、コンテクストを(この場合、近代劇特有のねじれ、個人と共同体の利益の相克)を提供することで、たやすく構造内の意味づけを新たに与えることができる。その結果、あたらしい統一感を見出し、あらたな「作品」の誕生を認定することになる(われわれは、H. Bloom以降、その気になればクロノロジーを無視するようにさえなった)。ちょうどギリシア悲劇というオリジナルなき翻案について、伝承上のキャラクターによってでも物語の時間によってでもなく、詩人は、作品の因果的統一によって「作者」になるとアリストテレスが述べたように。そして、(2)事後的に与えられた、この“作家性”こそが、翻案にあらたな「作品」としての地位を与えるのではないか。しかも、受容美学を経過した現代に生き、「作者の死」というスローガンに馴染んでいるにもかかわらずにである。今なお支配的な、“創造”の近代的な幻想は、翻案をたやすく作品へと変換してしまうのである(Greek Tragedies as/in Adaptations: The Poetics of Fragments and Body, 15th International Congress of Aesthetics, 30 August, 2001)。
以上に加えて、デ・ヨング教授には、アリストパネスによるエウリピデス作品の多彩なパロディをもつ喜劇『テスモポリアズーサイ』についての小論を提出したが、こちらについては省略する(Intertextuality in Aristophanes' Thesmophoriazousae, Aesthetics 10, 2002)。教授は、ギリシア劇の翻案研究を上演様式研究と並んで重要であるとし、オックスフォード大学で進行中のアーカイヴを紹介してくださったが、しかし「物語(narrative)とperformanceには厳然とした区別がある」ことを強調された。そこには、作品・翻案の序列と、作品・演出・上演という問題圏を重ねて見るわたしの研究計画への批判がこめられていたのかも知れない。しかし、翻案が作品へとすくい上げられるのと同様の事情によって、すなわち個々の演出・上演もまた、その“作家性”を認められることによって、現代では作品としての地位を獲得しつつあるのではないか。演出家の死後も各地の歌劇場で受け継がれる「ポネル演出」、そして氾濫するリミックス群に付される有名DJの名前など、──鍵は固有名詞、作者項の再生であるとおもわれる。
あるいは、個々の演出自体が、既に翻案の様相を示しているとしたらどうか。そもそもは三人に限られた俳優により(仮面の交換で多数の役柄を処理しつつ)上演されていたギリシア悲劇(入退場の工夫により、その処理はテクストに構造化されている)を、ふんだんに俳優を投入し俳優=役柄のアイデンティティーを保持しつつ進行する「蜷川演出」と、原作小説を他のメディアに、たとえば映画へと翻案することの間には、程度の違いしかないのではないか。この時、むしろ警戒すべきは、諸翻案、諸演出のステイタスの違いを、どう分析していくかということである。もちろん、新たな序列を試みてオリジナルへの憧憬に賛辞をおくってはならないだろう。
日時:4月26日(土)午後3:00-6:00
会場:京都大学文学部東館4階(北東角)COE研究室
環境問題における一元性と多元性
―移入種の排除をめぐる意思決定の問題
瀬戸口 明久(文学研究科博士課程)
上演芸術に見る翻案と演出
──アムステルダム大学における研修報告をかねて
若林 雅哉(文学部非常勤講師)
※PaSTA研究会の電子メール通知をご希望の方は事務局までご連絡下さい。